■ 連載:“こんな教室があったらいいのに”をかたちにするまで
■□ 連載:脳バランサーキッズ2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第2回 “こんな教室があったらいいのに”をかたちにするまで
──迷いながら、でも諦めずに立ち上げた最初の場所──
───────────────────────────────────…‥・
こんにちは。コアファイズ株式会社の山田広恵です。
前回は、「なぜこの事業を始めようと思ったのか」について、息子の育ちや葛藤を交えながら書かせていただきました。今回は、その想いをどうやって“かたち”にしていったのか──最初の教室を立ち上げるまでの過程について綴らせていただきます。
■ はじまりは、“想い”を重ねるところから
実は、最初の教室となる物件は、すでに決まっていました。
親会社のもとで新たに立ち上がる療育事業。その一施設として、この物件が用意されていたのです。
けれど、「ただの場所」としてではなく、“私がつくりたかった教室”にしていくためには、ここからが本当のスタートでした。
私が最初に向き合ったのは、制度の理解でした。
児童発達支援事業とは何か。どんな基準で、どう運営されるべきなのか。
許認可をいただくための要件や仕組みを、ゼロから必死に学びました。
同時に、療育に関する障害理解、そして「コアヴィレッジ」という教室名に込める意味や、内装の雰囲気、子どもたちの動線設計なども、ひとつひとつ考えていきました。
“与えられた空間”を、“願ってきた場所”に変えていく──。
それは、現実と理想のあいだで揺れながらも、想いを重ね続ける毎日でした。
■ 教室の設計は、“母目線”と“違和感の記憶”から
教室の設計を考えるうえで、私が頼りにしたのは、かつて療育施設を見学したときに感じた“違和感”でした。
それをひとつずつ丁寧に“反転”させていく作業から、すべてが始まりました。
「幼く感じた内装」──だったら、年齢にふさわしい落ち着いたデザインにしよう。
「静かすぎる空間」──だったら、子どもたちの声が自然に響いても安心できるようなつくりにしよう。
「ただ“支援を受ける場所”」ではなく、「子ども自身が“やってみたい”と思える空間」に。
そして何より、保護者の方々にとっても、「未来が楽しみになるような空間」であることを目指しました。
私は建築の専門家ではありません。
けれど、ブライダルの仕事で数多くの“人生の特別な場所”づくりに関わってきました。
主役の気持ちを大切にしながら空間をデザインするという経験は、子どもたちとそのご家族に向き合うこの教室づくりにも、自然と重なっていったのです。
「コアヴィレッジ」という教室名を決めたあと、ロゴとビジュアルデザインは、ブライダル時代から信頼しているデザイン会社にお願いしました。
ロゴのモチーフは、“幸せの象徴”とされるフクロウ。
夜でも遠くを見通すフクロウのように、子どもたちが未来を見つめ、自分の力で歩んでいけるように──そんな願いを込めました。
※コアヴィレッジのロゴ

内装設計については、同じくブライダル時代から何度もタッグを組んできた空間デザインのパートナー会社に依頼しました。
代表の方が、私の想いやビジョンをくみ取りながら、細部まで丁寧にディレクションしてくださいました。
打ち合わせを重ねるたびに、「ここなら子どもたちが自然体で過ごせる」と思える空間に近づいていくのが実感できました。
さらに、療育の専門的な視点からのアドバイスも欠かせないと考え、内装設計の最終確認では、五藤先生にもご相談させていただきました。
先生は、動線や視覚的な刺激、空間の見え方まで細かくご助言くださり、安心と機能性の両立が実現しました。
※コアヴィレッジ日本橋教室

※同


ブライダル事業で信頼を築いてきたデザイナーや設計パートナー、そして療育の専門家である五藤先生という、立場も背景も異なる方々と力を合わせながら、教室をかたちにしていきました。
その一人ひとりの力があったからこそ、コアヴィレッジの最初の教室は、“想いの宿る場所”として命を吹き込まれたのだと、心から感じています。
■ 「区との交渉」は、想像以上に壁が高かった
施設を運営するには、行政とのやりとりが欠かせません。
ブライダル事業から福祉事業へという異色の経歴である私だったからか、児童発達支援事業の新設に対して慎重な姿勢がありました。
何度も何度も、申請に足を運び、想いを説明し、書類を整えては差し戻されて…。
当初描いていたスタート月も超えてしまい、「なぜ児童福祉の門はこんなに遠いのだろう」
そう感じることもありました。
それでも続けられたのは、「息子や友人の子どもたちのような“グレーゾーン”の子が、安心して過ごせる場所を自分でつくる」という覚悟があったからです。
最終的に、申請が通ったときは、嬉しさよりも「やっと、ここからスタートできる」―――その一言に尽きます。
■ 保護者対応──“支援を提供する側”になるということ
開所してしばらくの間、私は施設の管理者として、東京と兵庫を行き来しながら、週の半分ほどは現場に足を運んでいました。
当時、まだ関西に自宅がありましたが、「想いを伝える最初の場面には、必ず自分が立ち会いたい」と思っていたのです。
新しく通ってくださる保護者の方々には、サービスの内容や教室の方針を、私自身の言葉でご案内していました。
私は専門家ではありませんが、「子どものことで悩んできた一人の親」として、心から語りかけたいと思っていました。
「私は専門職ではありません。でも、あなたの気持ちは、少しわかるかもしれません」
そんな想いをこめて、目の前のお母さん・お父さんに向き合い、ひとつひとつ丁寧にお話しするようにしていました。
“施設の代表”としてではなく、“母として”の言葉が、きっと必要だと思ったのです。
■ スタッフとの出会いが、すべてを前に進めてくれた
そして何より、支えとなったのが、スタッフとの出会いでした。
「現場を知らない自分が、スタッフにどう信頼してもらえるか」そんな葛藤もありました。
でも、私が「こんな教室をつくりたい」と語ると、真剣に耳を傾け、時に助言をくれ、現場に合うように調整しながら一緒に走ってくれる人たちがいます。
私は、「現場の声を一番に尊重しよう」と決めました。
なぜなら、子どもたちに一番近い場所にいるのは、支援者であるスタッフだからです。
制度よりも、理論よりも、“実感に根ざした運営”を。
今ではどの教室にも、信頼できるスタッフがいて、それぞれの子どもたちに心から向き合ってくれています。
■ 最後に──最初の扉が開いた日
最初の教室で、初めて子どもたちの声が響いた日。
「やっと、場所になれた」と、胸がいっぱいになったのを今でも覚えています。
すべての始まりは、小さな違和感でした。
「うちの子だけ…?」という言葉にならない気づき。
でも、あのときの想いが、今、こうして“共感できる誰か”に届く場となりました。
次回は、複数の教室を展開するなかでの気づきや、今後のビジョンについてお話ししたいと思います。どうぞ引き続き、お読みいただけたら嬉しいです。
◆山田広恵
TV局で報道やイベント企画・運営に携わった後、結婚を機にブライダル業界へ転身。全国展開企業のエリアマネージャーや独立後の経営を経て、2024年3月にブライダル事業を譲渡。現在は、東京都内に3教室、さいたま市内に2教室を展開する児童発達支援事業の経営・運営に専念している。直営の教室である「コアヴィレッジ」では、子どもの得意・不得意を科学的に分析し、苦手の克服や自立支援だけでなく、“当たり前”の一歩先を目指した支援を提供している。
第8回 脳バランサーキッズ2
───────────────────────────────────…‥・
しばらく間隔が空きましたが、レデックスのサービス紹介第8回です。
第6回で紹介したサービスをクラウド化し、より使いやすいサービス、脳バランサーキッズ2(脳キッズ2)としましたのでご紹介させていただきます。
※過去の連載 脳バランサーキッズ
1.新タスク追加で、17種類の充実した構成
英才塾として著名な花まる学習会で長年使われたパズルを中心にし、加えて世界でもっとも使われている注意力検査「トレイルメイキングテスト(TMT)」や文部科学省が子どもの抑制力(キレやすさ)の調査に使用した「ゴー・ノーゴー(go/no-go)」など定評ある発達検査を基に開発したゲーム(タスク)で構成しています。今回はさらに4種類を追加し、子どもが楽しんで使える17種類のタスク※1を用意しました。
※1 17種類のタスク

2.子どもの特性を把握しやすい認知機能の構成で表現
タスクの取組結果を6種類の認知機能(注意・抑制、言語理解、記憶、協調運動、推理・応用、視空間認知)※2に分析して、発達指数として数値化・グラフ化し、レポートを半自動で作成します※3。このレポートは特別支援学級や放課後等デイサービスで作成する個別支援計画の根拠として活用できます。保護者にもお子さんの発達の様子が分かりやすく、学校や施設と目線を合わせての支援に利用できます。
※2 6種類の認知機能

※3 レポート例

3.特許に基づく毎回異なる課題
レデックスの特許に基づき、毎回異なるタスクが出題されるので、取り組み間隔が短くても、正しい結果(発達指数)を得ることができます。専門士がいなくても、子どもが自由に取り組むことができ、知りたい日にちを指定すれば、自動的に記録された発達指数を確認できます。
※4 ウェクスラー式児童用知能検査との比較

4.クラウド化による利便性
前サービスを使うにはWindowsタブレットを用意する必要がありましたが、脳キッズ2は、ブラウザが動作するほとんどのタブレット、パソコン、スマホで使うことができます※4。学校や施設が保有するタブレット等をそのまま利用することができるのは、導入のハードルを格段に下げられます。
※5 OSフリーで広がる利便性

5.子どもだけで使い始められる「おうちログイン」
子ども一人ひとりの情報に紐づいた二次元コード※6を発行する機能を用意しました。支援者が事前準備をしなくても、子どもは自分の二次元コードを取り出し、それをタブレットのカメラで読むだけで使い始めることが可能です。
※6 おうちログイン

6.個別支援計画の作成に使え、支援のヒントを解説するガイドブック(PDF)
本サービスの結果を活用して、個別支援計画の作成や一人ひとりに合わせた支援方法の考案、子どもたちを伸ばしていく様々な活動アイデアを40ページ超の豊富な内容のガイドブックで解説しています。
※7 ほうかごアシスタント2ガイドブック目次

7.利用者データ・コンバータ
前サービスの利用者が、子どもの生年月日などの情報を脳キッズ2ですぐに使えるように、利用者データのコンバータを用意しました。脳キッズ2の管理者用のサポートページでは、こういった便利なツールやサービスを今後も充実させていく予定です。
8.支援者の理解を容易にする操作説明動画
脳キッズ2の利用方法からアセスメントの基本知識まで、脳キッズ2のさまざまな側面を5分から7分の動画で学べるように操作説明動画を用意しています。見終わると動画のポイントを確実に理解できるように、確認テストを用意しています。
25年8月現在、8本の動画を脳キッズ導入施設向けに公開しており、今後もさらなる充実を図っていく予定です。
※8 操作説明動画一覧

※9 操作動画画面例1

※10 操作動画画面例2

9.オンライン相談と初月無料
脳キッズ2の概要と使いかたを実際の画面で紹介するためにオンライン相談※11を用意しています。多数の自治体で研修を担当した経験を持つ五藤が対応しています。
さらに効果を確認して使い始められるように、申し込んだ月は無料で提供しています。利用期間のしばり等の制約もいっさいなく、安心して使い始めていただくことができます。
※11 オンライン相談
10.さらなる精度を高めるための標準化
東京の2つの保育園と愛知の小学校の協力を得て、3歳から12歳まで1学年40名程度の脳キッズ2の成績から正しい発達指数を得るための作業を行っており、25年9月には実装する予定です。前サービスでは参考値として使っていたかんたんモード(やさしい課題だけが出題)でも正しい発達指数が算出されるようになります。
※12 標準化のための基礎データ

標準化の実装後に、改めて、WISC-Vとの相関を調査する計画で、一層、子どもの特性を知るためのツールとして強化していけると思います。
◆五藤博義
本メルマガ編集長
■□ あとがき ■□--------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:「“うちの子だけ…?”から始まった、もうひとつの歩み」──母として、そして経営者として──第2回 “こんな教室があったらいいのに”をかたちにするまで
──迷いながら、でも諦めずに立ち上げた最初の場所──
───────────────────────────────────…‥・
こんにちは。コアファイズ株式会社の山田広恵です。
前回は、「なぜこの事業を始めようと思ったのか」について、息子の育ちや葛藤を交えながら書かせていただきました。今回は、その想いをどうやって“かたち”にしていったのか──最初の教室を立ち上げるまでの過程について綴らせていただきます。
■ はじまりは、“想い”を重ねるところから
実は、最初の教室となる物件は、すでに決まっていました。
親会社のもとで新たに立ち上がる療育事業。その一施設として、この物件が用意されていたのです。
けれど、「ただの場所」としてではなく、“私がつくりたかった教室”にしていくためには、ここからが本当のスタートでした。
私が最初に向き合ったのは、制度の理解でした。
児童発達支援事業とは何か。どんな基準で、どう運営されるべきなのか。
許認可をいただくための要件や仕組みを、ゼロから必死に学びました。
同時に、療育に関する障害理解、そして「コアヴィレッジ」という教室名に込める意味や、内装の雰囲気、子どもたちの動線設計なども、ひとつひとつ考えていきました。
“与えられた空間”を、“願ってきた場所”に変えていく──。
それは、現実と理想のあいだで揺れながらも、想いを重ね続ける毎日でした。
■ 教室の設計は、“母目線”と“違和感の記憶”から
教室の設計を考えるうえで、私が頼りにしたのは、かつて療育施設を見学したときに感じた“違和感”でした。
それをひとつずつ丁寧に“反転”させていく作業から、すべてが始まりました。
「幼く感じた内装」──だったら、年齢にふさわしい落ち着いたデザインにしよう。
「静かすぎる空間」──だったら、子どもたちの声が自然に響いても安心できるようなつくりにしよう。
「ただ“支援を受ける場所”」ではなく、「子ども自身が“やってみたい”と思える空間」に。
そして何より、保護者の方々にとっても、「未来が楽しみになるような空間」であることを目指しました。
私は建築の専門家ではありません。
けれど、ブライダルの仕事で数多くの“人生の特別な場所”づくりに関わってきました。
主役の気持ちを大切にしながら空間をデザインするという経験は、子どもたちとそのご家族に向き合うこの教室づくりにも、自然と重なっていったのです。
「コアヴィレッジ」という教室名を決めたあと、ロゴとビジュアルデザインは、ブライダル時代から信頼しているデザイン会社にお願いしました。
ロゴのモチーフは、“幸せの象徴”とされるフクロウ。
夜でも遠くを見通すフクロウのように、子どもたちが未来を見つめ、自分の力で歩んでいけるように──そんな願いを込めました。
※コアヴィレッジのロゴ
内装設計については、同じくブライダル時代から何度もタッグを組んできた空間デザインのパートナー会社に依頼しました。
代表の方が、私の想いやビジョンをくみ取りながら、細部まで丁寧にディレクションしてくださいました。
打ち合わせを重ねるたびに、「ここなら子どもたちが自然体で過ごせる」と思える空間に近づいていくのが実感できました。
さらに、療育の専門的な視点からのアドバイスも欠かせないと考え、内装設計の最終確認では、五藤先生にもご相談させていただきました。
先生は、動線や視覚的な刺激、空間の見え方まで細かくご助言くださり、安心と機能性の両立が実現しました。
※コアヴィレッジ日本橋教室
※同
ブライダル事業で信頼を築いてきたデザイナーや設計パートナー、そして療育の専門家である五藤先生という、立場も背景も異なる方々と力を合わせながら、教室をかたちにしていきました。
その一人ひとりの力があったからこそ、コアヴィレッジの最初の教室は、“想いの宿る場所”として命を吹き込まれたのだと、心から感じています。
■ 「区との交渉」は、想像以上に壁が高かった
施設を運営するには、行政とのやりとりが欠かせません。
ブライダル事業から福祉事業へという異色の経歴である私だったからか、児童発達支援事業の新設に対して慎重な姿勢がありました。
何度も何度も、申請に足を運び、想いを説明し、書類を整えては差し戻されて…。
当初描いていたスタート月も超えてしまい、「なぜ児童福祉の門はこんなに遠いのだろう」
そう感じることもありました。
それでも続けられたのは、「息子や友人の子どもたちのような“グレーゾーン”の子が、安心して過ごせる場所を自分でつくる」という覚悟があったからです。
最終的に、申請が通ったときは、嬉しさよりも「やっと、ここからスタートできる」―――その一言に尽きます。
■ 保護者対応──“支援を提供する側”になるということ
開所してしばらくの間、私は施設の管理者として、東京と兵庫を行き来しながら、週の半分ほどは現場に足を運んでいました。
当時、まだ関西に自宅がありましたが、「想いを伝える最初の場面には、必ず自分が立ち会いたい」と思っていたのです。
新しく通ってくださる保護者の方々には、サービスの内容や教室の方針を、私自身の言葉でご案内していました。
私は専門家ではありませんが、「子どものことで悩んできた一人の親」として、心から語りかけたいと思っていました。
「私は専門職ではありません。でも、あなたの気持ちは、少しわかるかもしれません」
そんな想いをこめて、目の前のお母さん・お父さんに向き合い、ひとつひとつ丁寧にお話しするようにしていました。
“施設の代表”としてではなく、“母として”の言葉が、きっと必要だと思ったのです。
■ スタッフとの出会いが、すべてを前に進めてくれた
そして何より、支えとなったのが、スタッフとの出会いでした。
「現場を知らない自分が、スタッフにどう信頼してもらえるか」そんな葛藤もありました。
でも、私が「こんな教室をつくりたい」と語ると、真剣に耳を傾け、時に助言をくれ、現場に合うように調整しながら一緒に走ってくれる人たちがいます。
私は、「現場の声を一番に尊重しよう」と決めました。
なぜなら、子どもたちに一番近い場所にいるのは、支援者であるスタッフだからです。
制度よりも、理論よりも、“実感に根ざした運営”を。
今ではどの教室にも、信頼できるスタッフがいて、それぞれの子どもたちに心から向き合ってくれています。
■ 最後に──最初の扉が開いた日
最初の教室で、初めて子どもたちの声が響いた日。
「やっと、場所になれた」と、胸がいっぱいになったのを今でも覚えています。
すべての始まりは、小さな違和感でした。
「うちの子だけ…?」という言葉にならない気づき。
でも、あのときの想いが、今、こうして“共感できる誰か”に届く場となりました。
次回は、複数の教室を展開するなかでの気づきや、今後のビジョンについてお話ししたいと思います。どうぞ引き続き、お読みいただけたら嬉しいです。
◆山田広恵
TV局で報道やイベント企画・運営に携わった後、結婚を機にブライダル業界へ転身。全国展開企業のエリアマネージャーや独立後の経営を経て、2024年3月にブライダル事業を譲渡。現在は、東京都内に3教室、さいたま市内に2教室を展開する児童発達支援事業の経営・運営に専念している。直営の教室である「コアヴィレッジ」では、子どもの得意・不得意を科学的に分析し、苦手の克服や自立支援だけでなく、“当たり前”の一歩先を目指した支援を提供している。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:サービスとアプリ-目標と由来第8回 脳バランサーキッズ2
───────────────────────────────────…‥・
しばらく間隔が空きましたが、レデックスのサービス紹介第8回です。
第6回で紹介したサービスをクラウド化し、より使いやすいサービス、脳バランサーキッズ2(脳キッズ2)としましたのでご紹介させていただきます。
※過去の連載 脳バランサーキッズ
1.新タスク追加で、17種類の充実した構成
英才塾として著名な花まる学習会で長年使われたパズルを中心にし、加えて世界でもっとも使われている注意力検査「トレイルメイキングテスト(TMT)」や文部科学省が子どもの抑制力(キレやすさ)の調査に使用した「ゴー・ノーゴー(go/no-go)」など定評ある発達検査を基に開発したゲーム(タスク)で構成しています。今回はさらに4種類を追加し、子どもが楽しんで使える17種類のタスク※1を用意しました。
※1 17種類のタスク
2.子どもの特性を把握しやすい認知機能の構成で表現
タスクの取組結果を6種類の認知機能(注意・抑制、言語理解、記憶、協調運動、推理・応用、視空間認知)※2に分析して、発達指数として数値化・グラフ化し、レポートを半自動で作成します※3。このレポートは特別支援学級や放課後等デイサービスで作成する個別支援計画の根拠として活用できます。保護者にもお子さんの発達の様子が分かりやすく、学校や施設と目線を合わせての支援に利用できます。
※2 6種類の認知機能
※3 レポート例
3.特許に基づく毎回異なる課題
レデックスの特許に基づき、毎回異なるタスクが出題されるので、取り組み間隔が短くても、正しい結果(発達指数)を得ることができます。専門士がいなくても、子どもが自由に取り組むことができ、知りたい日にちを指定すれば、自動的に記録された発達指数を確認できます。
※4 ウェクスラー式児童用知能検査との比較
4.クラウド化による利便性
前サービスを使うにはWindowsタブレットを用意する必要がありましたが、脳キッズ2は、ブラウザが動作するほとんどのタブレット、パソコン、スマホで使うことができます※4。学校や施設が保有するタブレット等をそのまま利用することができるのは、導入のハードルを格段に下げられます。
※5 OSフリーで広がる利便性
5.子どもだけで使い始められる「おうちログイン」
子ども一人ひとりの情報に紐づいた二次元コード※6を発行する機能を用意しました。支援者が事前準備をしなくても、子どもは自分の二次元コードを取り出し、それをタブレットのカメラで読むだけで使い始めることが可能です。
※6 おうちログイン
6.個別支援計画の作成に使え、支援のヒントを解説するガイドブック(PDF)
本サービスの結果を活用して、個別支援計画の作成や一人ひとりに合わせた支援方法の考案、子どもたちを伸ばしていく様々な活動アイデアを40ページ超の豊富な内容のガイドブックで解説しています。
※7 ほうかごアシスタント2ガイドブック目次
7.利用者データ・コンバータ
前サービスの利用者が、子どもの生年月日などの情報を脳キッズ2ですぐに使えるように、利用者データのコンバータを用意しました。脳キッズ2の管理者用のサポートページでは、こういった便利なツールやサービスを今後も充実させていく予定です。
8.支援者の理解を容易にする操作説明動画
脳キッズ2の利用方法からアセスメントの基本知識まで、脳キッズ2のさまざまな側面を5分から7分の動画で学べるように操作説明動画を用意しています。見終わると動画のポイントを確実に理解できるように、確認テストを用意しています。
25年8月現在、8本の動画を脳キッズ導入施設向けに公開しており、今後もさらなる充実を図っていく予定です。
※8 操作説明動画一覧
※9 操作動画画面例1
※10 操作動画画面例2
9.オンライン相談と初月無料
脳キッズ2の概要と使いかたを実際の画面で紹介するためにオンライン相談※11を用意しています。多数の自治体で研修を担当した経験を持つ五藤が対応しています。
さらに効果を確認して使い始められるように、申し込んだ月は無料で提供しています。利用期間のしばり等の制約もいっさいなく、安心して使い始めていただくことができます。
※11 オンライン相談
10.さらなる精度を高めるための標準化
東京の2つの保育園と愛知の小学校の協力を得て、3歳から12歳まで1学年40名程度の脳キッズ2の成績から正しい発達指数を得るための作業を行っており、25年9月には実装する予定です。前サービスでは参考値として使っていたかんたんモード(やさしい課題だけが出題)でも正しい発達指数が算出されるようになります。
※12 標準化のための基礎データ
標準化の実装後に、改めて、WISC-Vとの相関を調査する計画で、一層、子どもの特性を知るためのツールとして強化していけると思います。
◆五藤博義
本メルマガ編集長
■□ あとがき ■□--------------------------


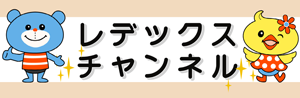
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




