■ はじめに
■□ 新連載:ベネッセ特別協賛シリーズ:特性による学びづらさに寄り添う
■□■ 新連載:“うちの子だけ…?”から始まった、もうひとつの歩み
■□■ 新連載:“うちの子だけ…?”から始まった、もうひとつの歩み
--------------------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
本メルマガ編集の五藤です。今回から始まる新しい連載をご紹介します。
一つは、私が起業前に勤務していた株式会社ベネッセコーポレーションとの協賛による連載「特性による学びづらさに寄り添う」です。
ベネッセは2024年から〈まるぐランド for HOME〉という新しい学習サービスを始めています。そのサービスでは、学びづらさを抱えたお子さまに対して、その子の特性に合わせてタブレット学習とオンライン個別指導を組み合わせた学習支援を行っています。そこでは、1人ひとりのお子さんと保護者に向き合い、自己肯定感を高めていく指導を行っており、その監修をされている先生がたから3回に渡ってご寄稿いただけることになりました。
もう一つは、東京都内とさいたま市内で複数の放課後等デイサービスと児童発達支援サービスを運営されているコアファイズ株式会社社長の山田広恵さんの連載です。
山田さんはご自身のお子さんが発達の困りをもつという状況に遭遇され、その解決を求める過程で、児童福祉施設を立ち上げるという決断をされました。そのご経験を3回の連載で語っていただきます。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:ベネッセ特別協賛シリーズ:特性による学びづらさに寄り添う第1回 保護者に“寄り添う”支援のカタチ―現場でできる心のサポート
───────────────────────────────────…‥・
子どもを取り巻く環境は、ここ数年で急速に変化しています。その背景には少子化の進行があり、政策面でも「こども基本法」の制定や「こどもまんなか社会」の実現など、子どもに焦点をあてた取り組みが進められてきました。「子どもを大切にしよう」という機運は年々高まっています。
このような動き自体は、日頃お子さんの支援をしている立場から見るととても歓迎すべきことです。しかし、その一方で、実際に子育てを担う保護者へのサポート――とくに日々の不安や悩みに寄り添う支援は、まだまだ十分とは言えないのが現状です。
これまでも出産費用や待機児童の問題など、子育てしやすい環境や制度を整える方向では議論や施策が進められてきました。ただ、「今まさに子育てをしている方」に寄り添うサポートが、果たしてどれだけ行き届いているのか。地域や自治体によって差があることも事実ですが、現場の実感としてはまだ手薄さが残ると感じています。
では、保護者に寄り添ったサポートとは具体的にどのようなものなのか。また、どのような関わり方が求められているのか。今回は、私自身の臨床経験も踏まえながら、3つの「寄り添う」視点について考えてみたいと思います。
■「不安」に寄り添う
子育てには、いつも「不安」がつきまといます。たとえば「何歳でどんなことができるようになる」といった発達の目安はありますが、日々起こる出来事は一人ひとり違い、保護者自身も手探りで育てている方が多いのが実際のところです。
もちろん、子育て雑誌や先に子育てを経験した友人・親戚のアドバイスに助けられる場面もあるでしょう。しかし、授業などで体系的に子育てを学ぶ機会はほとんどなく、仮にマニュアルがあったとしても、子どもの個性は千差万別。「この通りにすれば大丈夫」という確かな道筋は見えにくいものです。結局のところ、多くのご家庭が「手探り」で子育てをしているといえるでしょう。
人は見通しの立たない状況に強い不安を感じやすいといわれています。子どもがどう育つのか、新しいクラスにどうなじむのか……毎日が未知数の連続で、保護者の不安は尽きることがありません。
だからこそ、私たち支援する側は、「保護者は常に不安を抱えている」ということを前提にした関わり方が大切です。
たとえば、小学校1年生の保護者と接するとき。自分は「何度も見てきたから当たり前」に思えても、保護者にとっては初めての体験であり、不安でいっぱいです。教職や専門職を長く続けていると、つい慣れが出てしまいがちですが、その都度の「初めて」に寄り添う気持ちは持ち続ける必要があるといえるでしょう。
また、発達障害などの特性があるお子さんを育てているご家庭の場合、「ここまでの育て方が合っていたのか」「将来どのような職につけるのか」「そのために今なにをすればいいのか」など、より見通しが立ちにくい分、不安もさらに大きくなります。
専門職であれば、検査や行動観察を通してある程度の見通しを伝えられることも多いですが、ご家庭は戸惑いの真っ只中。支援者ができるだけ具体的な見通しを伝えたり、「大丈夫ですよ」と寄り添う一言をかけたり、ひとりで抱え込まないよう伴走することが、何よりの支えになります。安心できる伴走者の存在は、保護者だけでなく、子どもの成長にもプラスになるはずです。
■「子どもを守りたい」に寄り添う
もうひとつ、大切なのは「子どもを守りたい」という気持ちへの寄り添いです。
たとえば、先生などに注意されたり叱責を受けた時、保護者自身に起こったことであれば「まあ、仕方がない」と流せるかもしれません。でも、それがわが子のこととなると、そう簡単には気持ちの整理がつきません。「うちの子は大丈夫かな」「本当は悪くなかったんじゃないか」と、より強く心配したり、不安になったりします。“自分ごと”より“子どもごと”のほうが心が敏感になりやすいのです。
また、何らかの障害や特性のあるお子さんの場合には、「周りの子ができていることができない」などと心配が膨らみ、「何とかしてあげたい」「守ってあげたい」という思いは、さらに強くなります。先生から何かを指摘されると、それが前向きな提案であっても「また言われてしまった」と落ち込むこともあれば、「どうしてうちの子を理解してくれないのか」と不安や苛立ちを感じることもあります。
こうした思いが時に支援者や指導者に直接ぶつけられることもありますし、逆にご家庭内でお子さんや保護者自身に向かってしまうこともあります。
この「子どもを守りたい」という思いに、支援者がしっかりと理解を示すこと――これが保護者との信頼関係を築く出発点です。「それだけお子さんのことを心配されているんですね」と受け止めていくと、難しいケースでも打開策が見えてくることがあります。「共にお子さんを支える」という協力体制も、そこから生まれていきます。
■「焦り」に寄り添う
子どもは日々、めまぐるしく成長します。気づけば歩けるようになり、自転車の練習をはじめたり、靴や服もどんどん大きくなっていきます。
そうしたスピードを実感している保護者ほど、「今これをやらなければ、よりよい成長を促せないのでは」と思い込み、焦りを感じることがあります。実際、「○歳までにこれをやっておかないといけない」といった子育て情報に溢れ、さらに焦りを助長することも少なくありません。
もちろん、心理学的には「○歳にこうしたことをしておくとよい」という知見はあります。ただ、何か特別な力を伸ばす場合を除けば、基本的には園や学校のカリキュラムに沿って、その時々の課題や遊びに向き合っていれば、無理に焦る必要はありません。もともと子どもの発達段階に合わせて内容が組まれていますので、自然な流れに身を任せるくらいの気持ちで十分なのです。
このように、もともと焦りがちな子育てですが、特に発達障害等の特性がみられる場合は、周囲の流れについていけなくなることも多く、保護者の焦りはさらに大きくなります。
「早期からの療育が必要」といわれますが、これは早めに対応した方が適応がしやすくなり、ご本人も保護者も楽になるからです。ただ、「今からでは遅い」ということはあまりない、というのが実感です。私のもとには小学校高学年を過ぎて初めて相談に来られるご家庭もありますが、どのお子さんもそれぞれに成長しています。その時点までの成長や個性をしっかり見つめて、その子なりの伸びしろを見つけて伸ばしていけば大丈夫。「今からでも大丈夫ですよ」と伝えつつ、「ではこれからどうしていくか、一緒に考えていきましょう」と、見通しを共に考えることが大切です。
また、焦りから「ドクターショッピング」や「教材ショッピング」といった形で、あれこれ手をつけてしまうケースについても触れておきたいと思います。
「この教材を使ってみたけど効果がなかったのでやめた」という話をよく耳にします。ただ、実際に詳しく伺うと、試したのは1週間程度、ということも少なくありません。本来効果を見定めるには少なくとも3か月くらいは腰を据えて取り組みたいところで、お子さんの特性によっては、もっと長い時間が必要なこともあります。お子さんがどうしても嫌がる場合は別ですが、どんなことでも効果が出るまでにはある程度時間をかける必要があります。
「始めてみたものの、すぐに効果が感じられないからやめてしまう」というのは、教材に限らず、療育や医療への通所・通院でもよく見られることです。
ここで大切なのは、支援者が、お子さんに必要なことや適した方法を専門的に伝えること、そしてそれを気長に見守れるようにサポートすることです。「すぐに結果がでなくても大丈夫。もう少し続けてみましょう」と伴走すること。さらに、日々の中でお子さんの成長に気づいてもらい、その成長を実感してもらうこと。少しずつでも育ちが実感できれば、焦りは継続につながり、また安心にもつながります。
子どもの成長は、どのお子さんも一直線ではありません。なかなかできないなと思っていたことでも、ふっと階段を上るようにできるようになる。成長にはタイミングがあります。そのタイミングを待ちながら、それぞれのお子さんに合ったはたらきかけを根気強く続けることの大切さを伝え、共に悩み、考えていくことが肝要です。
・・・
ここまで、臨床経験を踏まえて、保護者に寄り添う3つの視点をお話ししてきました。「こどもまんなか」と言われますが、実際に子どもを長い時間支えていくのは保護者です。適切な保護者支援は、子どもの心の安定や、よりよい成長に必ずつながっていきます。
子育て中は、大人も毎日大変な思いをしています。子育てをしているだけで、もう充分にがんばっているのです。「がんばっていますね」「時には自分の時間を持って、ほっとしてくださいね」と、そんな一言を添えながら、力を入れすぎずに支援していきたいですね。
◆山崎 衛
10年間の教職経験の後、株式会社マイン入社。マインEラボ・スペース代表を経て、現在ククア本郷ルーム代表。公認心理師、臨床発達心理士、特別支援教育士。
子供から大人まで生涯を見据えた、療育・学習支援・心理検査など心理発達支援に取り組む傍ら、学校向け研修や巡回相談、実践に基づいた学習教材の開発・出版、自治体のこども政策の立案にも携わっている。
株式会社ベネッセコーポレーションが2024年から新しく提供を開始した学習支援サービス〈まるぐランド for HOME〉の監修を務める。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:「“うちの子だけ…?”から始まった、もうひとつの歩み」──母として、そして経営者として──
第1回 なぜ私がこの事業を始めたのか
───────────────────────────────────…‥・
こんにちは。コアファイズ株式会社の山田広恵と申します。
この連載では、私自身の経験をもとに、子育てと児童福祉、そして事業への想いを綴らせていただきます。
第1回は、「なぜ私がこの事業を始めたのか」について、お話させてください。
■ “なんとなく気になる”という日常の違和感
「うちの子、ちょっと他の子と違うかもしれない…」
最初は本当に、些細な違和感からでした。
解釈の仕方、独特の発想、集団での行動、他の子との関わり方。
当時は母親や園の先生にも相談しましたが、返ってくるのは「男の子はこんなものよ」「育ちが少しゆっくりなだけよ」といった言葉でした。
たくさん励ましてもらったにもかかわらず、私の心はどうしても晴れませんでした。
育児本やネットの情報を読みながら、「育ちには個人差があるし、きっとそのうち落ち着いてくるはず」と、自分に言い聞かせていた日々。
でも、周囲の子どもたちが次のステップへ進んでいく中で、我が子だけがぽつんと立ち止まっているような気がして、焦りと不安が少しずつ大きくなっていきました。
■ “母親失格”と感じた日もありました
思い切って、かかりつけの小児科で相談してみたこともありました。
でも返ってきたのは、「まだ年齢的に様子を見ましょうかね」「お母さん、ちょっと考えすぎかもしれませんね」といった言葉でした。
そのときは一瞬ホッとしたような気持ちもありましたが、どこか突き放されたような、宙ぶらりんな気持ちが残りました。
誰にも言えず、夜な夜な検索をしたり、お友達の家に謝りに行くことも多く、「なんで私は子育てがうまくいかないんだろう…」と涙をこらえることもありました。
「私の育て方が悪かったのかな」「自分のせいでこの子が苦しんでいるのかも」と、自分を責めてしまう日もたくさんありました。
それでもその頃はすでに起業していたので、何も悩みなんてないように振る舞って、自分を取り繕っていました。
だからこそ、こうしてこの体験を文章にすること自体にも、最初はとても迷いがありました。
■ 希望を探しに行ったはずなのに
息子が小学生になった頃、担任の先生から「一度、相談してみては」と紹介されたのが、地域の相談窓口でした。
そこからいくつかの療育施設を見学することになりました。
けれど、正直に言うと…
私は、落ち込んで帰ってきました。
静まり返った古い室内。小学生の子どもたちが、まるで保育園のような空間で過ごしているように見えました。
「ここに通えば、この子の未来が少しでも開けるのでは」と期待していた分、違和感の方が強く残ってしまったのです。
見学に行ったのは私ひとりでしたが、落ち込みすぎてなかなか家に帰れませんでした。
「ここじゃない。この子が過ごすべき場所は、きっとどこか他にある」──そんな直感めいた思いが、胸の中に残りました。
■ 診断と向き合う。そして、大きな反省と決意
それから何年も時が流れ、息子が中学1年生になった頃のことです。
担任の先生から思いもよらない厳しい言葉をかけられたことをきっかけに、息子はチックの症状を見せるようになりました。
私も限界に近づいていたそのとき、長年悩みを見守ってくれていた親友が、「病院で一度、発達検査を受けてみたらどう?」と勧めてくれました。
「ママも〇〇(息子)も、きっと楽になるから。絶対に大丈夫だよ。」
そう優しく背中を押してくれたことがきっかけで、私はようやく病院に行く決意をしたのです。
そして出た診断は、ASD・ADHD。
「やっぱりそうだったんだ」と納得する一方で、もし何らかの診断がおりたとしたら、きっとASDではなくADHDだと思い込んでいた私の心に広がったのは大きな反省でした。
もっと早く気づいてあげられていたら。
幼い頃から、トレーニングできる環境を整えてあげられていたら。
あのとき、見学先の療育施設を「違う」と切り捨てるのではなく、もっと息子にとって必要な場として考えていたら──。
しばらく涙が止まりませんでした。
そして、過去に見学に行った施設の情景が頭に浮かびました。
「そっか。できる環境を私がつくればいいんだ」──そう、心の奥から静かに、でも確かに湧き上がってきたのです。
■ 専門職ではない私だからこそ見えた景色
もちろん、私は児童発達支援の専門職ではありません。
現場で子どもに直接関わることも、専門的な知識も持っていません。
それでも、「こんな教室があったらいいのに」と願ったあの日の気持ちだけは、ずっと変わりませんでした。
そして、その想いを理解し、一緒にかたちにしてくれたのが、出会ったスタッフたちです。
そして、教材・プログラム面で全面的に支えてくださったのが、五藤先生です。
先生がいなければ、今のコアヴィレッジの療育は存在しなかったと、心から思っています。
■ すべての“あの頃の私”へ
私は、子どもと家族の「これから」を支える場所をつくりたいと思っています。
子どもが安心して過ごせて、保護者も孤独を感じないでいられる場所。保護者と子どもが明るい未来を想像できる場所。
そして、スタッフ一人ひとりが誇りを持って働ける教室を。
私は現場に立てない分、「経営」という立場からその環境を守ることが、私の役割です。
スタッフたちは、日々学び、努力し、子どもたちの未来のために本気で向き合ってくれています。
私はそんな仲間たちを心から尊敬し、感謝しています。
この連載を読んでくださっている方の中に、かつての私のように、見えない不安の中で子育てと向き合っている方がいらっしゃるかもしれません。涙をこらえる日がたくさんあるのではないでしょうか。
どうか、ひとりで悩まないでください。
“うちの子だけ?”という小さな気づきは、何かが始まる大切な一歩です。
次回は、コアヴィレッジ最初の教室をどのように設計し、行政との交渉や保護者への説明にどう向き合ったかをお話しします。
引き続き、お読みいただけたら嬉しいです。
◆山田広恵
TV局で報道やイベント企画・運営に携わった後、結婚を機にブライダル業界へ転身。全国展開企業のエリアマネージャーや独立後の経営を経て、2024年3月にブライダル事業を譲渡。現在は、東京都内に3教室、さいたま市内に2教室を展開する児童発達支援事業の経営・運営に専念している。直営の教室である「コアヴィレッジ」では、子どもの得意・不得意を科学的に分析し、苦手の克服や自立支援だけでなく、“当たり前”の一歩先を目指した支援を提供している。
■□ あとがき ■□--------------------------
レデックスでは、今年4月からクラウド機能を使った脳バランサーキッズ2を提供しています。採用した施設向の支援に注力しており5~7分の動画で利用方法を学べます。現在、8本の動画を公開しており、セットの確認テストも好評です。アセスメントガイドブックは、全40ページ以上のボリュームで、はじめての方にも、もう一度学びたい方にもご満足いただける内容です。
今後も、ご導入いただいた施設の皆さまへのサポートに一層力を入れてまいります。
また、従来の脳バランサーキッズから脳キッズ2に移行される方向けに、登録利用者の生年月日などを脳キッズ2に移植する機能も今月からサポート開始しましたのでこの場をお借りしてご紹介させていただきます。
※脳バランサーキッズ2
次回メルマガは、7月11日(金)の刊行です。


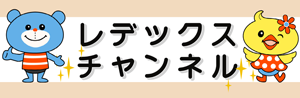
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




