■ はじめに
■□ 新連載:あまり知られていない発達障害のある人の疲労について
■□■ 連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ
■□■ 連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
今回から始まる連載についてご紹介します。
友人が日本疲労学会で知りあった研究者を紹介してくれ、その内容に興味をもってメルマガへの寄稿をお願いしたところ快諾してくださいました。
仲田真理子(なかた・まりこ)さんは筑波大で、ホルモンと社会行動の関係を調べる研究者です。その傍ら、ご自身が発達障害の当事者ということで、他の人とは異なった困りを多く抱えておられ、ご専門の神経科学の観点から、発達障害の人は疲れやすいのではないかということの研究を始められました。
編者自身、ADHDの診断を受けていることから共通の経験をもつことも多く、今回の4回の連載をとても楽しみにしております。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:あまり知られていない発達障害のある人の疲労について 第1回 発達障害があると疲れやすいって本当?:ADHDと疲労の関連
───────────────────────────────────…‥・
この連載では意外と知られていない「発達障害と疲労」について、これまでの研究や、当事者や家族からの視点をご紹介したいと思います。
「発達障害がある人は疲れやすい」というのは、本当でしょうか。
実際、発達障害の当事者同士で集まると「しんどいね、疲れるよね」という話題になることは非常に多いです。WilliamsとGotham (2022)が自閉スペクトラム症の当事者に対して行った調査では、「この1週間、次のような問題にどのぐらい悩まされていますか?」という質問に「疲れた感じがする、または気力がない」ことに悩まされていると回答した人は全体の7割を越え、15カテゴリに分けられた体調不良の中で堂々の1位にランクインしました(日本語の質問と選択肢は、村松, 2014より抜粋)。
ちなみに、2位は睡眠の問題、3位は女性の生理痛などの生理に関する問題だったそうです。当事者以外から見ても、疲労は発達障害のある人の抱える困難の一つである、という認識はされているようで、就労支援に関連する事業所等のウェブサイトでは、疲労の問題を取り上げているページが多くありますし、発達障害についての研究論文を調べると「疲労(fatigueあるいはtiredness)」という言葉をよく目にします。それでは、発達障害と疲労の関係については、どのような研究があるのでしょうか?「発達障害 疲労」というキーワードで論文を検索すると、発達障害のあるお子さんを育てるご家族の方の疲労についての研究が多くヒットします。その一方で、発達障害のある当事者の疲労については、生活を大きく圧迫する重要な問題であるにもかかわらず、研究のメイントピックになることがまだ少ないのが現状です。私は、このような状況を変えたいと強く思っています。
そもそも、疲労とは何なのでしょうか。疲労は「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態」と定義されています。そしてこのような状態があると、私たちは疲労が存在することの自覚である不快感と活動意欲の低下、すなわち「疲労感」を感じる場合が多いです(日本疲労学会)。海外の文献では、身体の状態である「疲労」とその自覚である「疲労感」を分けて考えることは少ないようで、疲労(fatigueまたはtiredness)自体が「An experience of tiredness, dislike of present activity, and unwillingness to continue.(疲労感と今やっている活動を行いたくない、続けたくないという経験;Bartley, 1970)」などと定義されています。
ちなみに、うつ病など様々な疾病で、全身倦怠感、だるさ、脱力感を感じるとされていますが、これは「疲労感」とほぼ同じ意味で用いられることが多いようです。
何らかの作業をやろうとしたり、やっている最中に独特の不快感があり、「その活動をしたくない」「続けたくない」気持ちが生じてその活動をストップしてしまう。発達障害の当事者である私は、物心ついた時から今まで、このような現象を1日に何度も経験してきました。私は、長い間、この現象が起こるのは「自分はやる気がない、努力ができないから」だと思っていました。しかし、今はそう考えていません。自分には疲れやすい性質があって、何かをしようとしても疲れていて着手できなかったり、何かをするとすぐ疲れてしまうのだと考えています。
読者の皆さんの中には、発達障害のある人が何かをしないのは「先延ばし」や「やり渋り」ではないのか?とお思いになる方もいらっしゃるでしょう。確かに、外から見た現象としてはそうかもしれません。私たち発達障害者が何かをしなかったりできなかったりするとき、感覚の問題や認知の問題に結び付けて考えることは多いですし、実際その解釈が当たっていることもあります。
また、発達障害のある人の脳では、モチベーションと大きく関係する「報酬系」という部位の活動が変化しているという報告(Dichterら, 2012など)もあり「やる気」が関連しているということも間違いではないでしょう。
一方で、発達障害のある人が、工夫や配慮によって感覚の問題や認知能力の問題に対策ができていたとしても、学校や仕事に行くことが難しくなる場合があります。「疲労」という視点から考えることで、このような感覚や認知、そしてモチベーションの問題だけでは説明できない現象の謎を解くことができると思っています。
では、発達障害のある人のどのような特性が疲労と関連しているのでしょうか。
まずは、私の研究テーマでもある、注意欠如多動症(ADHD)と疲労の研究を紹介します。Rogersら(2017)は、ADHDと診断された人と医学的な診断がない、すなわち疾病のない人たちに、「チャルダーの疲労スケール」という尺度(質問紙のこと; 日本語版は花輪ら, 2002; 新しいバージョンはCella & Chalder, 2010)で、最近1か月の疲労感について尋ねました。すると、ADHDの人たちは、疾病のない人たちよりも有意に疲労感が強いことが分かりました。
ADHDの特性は、注意のコントロールが難しい「不注意特性」と、活動量が多かったり衝動をコントロールすることが難しい「多動衝動性」のふたつの側面に分けて測ることができます(Kesslerら, 2005)。これまでの研究では、ADHDで不注意特性の強い「不注意優勢型ADHD」の人は、混合型の人よりも疲れやすいという報告(Yoonら, 2013)があります。私たちが行った調査でも診断の有無にかかわらず不注意特性のほうが疲労感と強く関連するという結果が得られていることから(仲田ら, 2024)、どうも注意のコントロールが難しいという特性が疲労と関連するようです。
それでは「不注意優勢型ADHD」の人は、全員が疲れやすいのでしょうか?
確かに診断のある人とない人で比べると統計的な差がありますが、ADHDの診断がつく人たちの中にも、疲労感の程度には大きな個人差があるのではないかと考えられます。ADHDの診断基準を満たす成人の45%程度が該当すると言われる、Cognitive disengagement syndrome (CDS)という症状があります(Barkley, 2012)。かつてはSluggish Cognitive Tempo (SCT)と言われていましたが、ネーミングが侮蔑的(Sluggishとは「動きや動作が鈍い」の意)なので改名されたようです(Becker et al., 2023)。
この症状の程度を測る尺度は、日本語にも翻訳されています(砂田ら、2018)。CDSは、「一日中けだるい感じがする」「無気力でやる気がない」「動くのがおっくうに感じる」など、疲労感とも共通するような症状が特徴で、先述したRogersら(2017)の論文では、ADHDがあることと疲労の問題が関連する証拠のひとつとして紹介されています。
CDSのある人は、そうでないADHDの人と比べて、仕事や家事、人間関係や子育てなど日常生活のすべての面で機能障害の程度が大きいことが報告されており(Barkley, 2012, 2013)、これは、当事者である私も体感しています。現在私は大学教員として働いているのですが、この仕事をしているとわりと頻繁にADHD仲間に出会います。その中にはフルタイムの職に就いている人もたくさんいるのですが、自分と同じ「疲れやすいタイプ」に出会うことはほとんどありません。ADHD者の約半分は自分と似たような症状を持っているはずなのに、社会のなかで、発言力のあるポジションについている仲間はおそらくとても少ないのです。このことが、疲労の研究を自分がしなければ、と思った理由のひとつでもあります。
第2回は、自閉スペクトラム症(ASD)と疲労の関連について紹介し、疲労の生物学的メカニズムにも触れながら、発達障害と疲労について引き続き考えていきたいと思います。
引用文献
Barkley, R. A. (2012). Distinguishing sluggish cognitive tempo from attention-deficit/hyperactivity disorder in adults. Journal of Abnormal Psychology, 121, 978?990.
Barkley, R. A. (2013). Distinguishing sluggish cognitive tempo from ADHD in children and adolescents: Executive functioning, impairment, and comorbidity. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 42, 161?173.
Bartley, S. H. (1970). The homeostatic and comfort perceptual systems. The Journal of Psychology, 75(2), 157-162.
Becker, S. P., Willcutt, E. G., Leopold, D. R., Fredrick, J. W., Smith, Z. R., Jacobson, L. A., ... & Barkley, R. A. (2023). Report of a work group on sluggish cognitive tempo: Key research directions and a consensus change in terminology to cognitive disengagement syndrome. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 62(6), 629-645.
Cella, M., & Chalder, T. (2010). Measuring fatigue in clinical and community settings. Journal of psychosomatic research, 69(1), 17-22.
Dichter, G., Damiano, C., & Allen, J. (2012). Reward circuitry dysfunction in psychiatric and neurodevelopmental disorders and genetic syndromes: animal models and clinical findings. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 4, 19 - 19.
花輪治子,中野弘一,筒井未春,簑輪眞澄,土井由利子. (2002). チャルダー疲労質問票日本語版の作成について.第7回慢性疲労症候群(CFS)研究会, 大阪. 第7回慢性疲労症候群(CFS)研究会講演要旨集.p. 38.
Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E. V. A., ... & Walters, E. E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): a short screening scale for use in the general population. Psychological medicine, 35(2), 245-256.
村松公美子. (2014). Patient Health Questionnaire (PHQ-9, PHQ-15) 日本語版および Generalized Anxiety Disorder-7 日本語版-up to date- 新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究, Vol.7 35-39.
仲田 真理子, 長濱 奈甘乃, 小清水 想, 瀬戸川 剛. (2024). 日常生活行為によって引き起こされる疲労感とADHD 特性の関連. 第20回日本疲労学会総会・学術集会. 大阪.
砂田安秀, 甲田宗良, 伊藤義徳, & 杉浦義典. (2018). ADHD 併存症状である Sluggish Cognitive Tempo の成人版尺度の開発――抑うつとの弁別を目的として. パーソナリティ研究, 26(3), 253-262.
Rogers, D. C., Dittner, A. J., Rimes, K. A., & Chalder, T. (2017). Fatigue in an adult attention deficit hyperactivity disorder population: A trans‐diagnostic approach. British Journal of Clinical Psychology, 56(1), 33-52.
Williams, Z. J., & Gotham, K. O. (2022). Current and lifetime somatic symptom burden among transition‐aged autistic young adults. Autism Research, 15(4), 761-770.
Yoon, S. Y. R., Jain, U. R., & Shapiro, C. M. (2013). Sleep and daytime function in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: subtype differences. Sleep medicine, 14(7), 648-655.
◆仲田真理子(なかた・まりこ)
筑波大学人間系助教。
専門は行動神経内分泌学。ホルモンと社会行動の研究の傍ら、疲労の研究をはじめる。自身が発達障害(自閉スペクトラム症/ASD・注意欠如多動症/ADHD)の当事者であることから、発達障害のある人のための通院・服薬に関する理解促進パンフレット「発達障害の当事者とまわりの人のための薬はじめてガイド」を制作し、無料で配布する活動を続けている。パンフレットは、webサイトよりアクセシブルPDF版をダウンロードできるほか、サイト内の「お申し込みフォーム」より無料で紙の冊子の発送を依頼することができる(病院や学校などには、一度に大量に発送することも可能)。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:小児科医の私が、起業してアプリを作っているわけ 第2回 「アナタの視点」にワタシが気づくことの大切さ
───────────────────────────────────…‥・
前回の記事で私は「言われたことを一瞬でイラストに変えてくれるアプリ」を作った話をしました。
今回の記事では、このアプリが私たちのコミュニケーションにどのような価値をもたらすか、もう少し詳しく書かせていただこうと思います。
■ タマゴだけど、タマゴじゃないの
「さすがに、怒りましたよ。タマゴ食べたいって言ったのはお前だろ? だからわざわざ焼いてやったのに、なに考えてんだーって……」
不穏な空気をまとって診察室に入ってこられたお父様に伺うと、朝の出来事が見えてきました。彼女は今朝、お父様がせっかく焼いてくださった目玉焼きを前にして盛大に癇癪を起こし、来院前にご自宅で、ひと悶着あったようなのです。
「もしかしてだけどさ、食べたかったのって……」
私は彼女の前に、何枚かのイラストを並べてみました……
※ 目玉焼きと、卵焼きと、ゆで卵と、スクランブルエッグのイラスト
彼女は迷わず、左から二番目の「卵焼き」を指して
「タマゴ!」
と叫びます。
「えっ!? ぜんぶ『タマゴ』だよ……」
お父様が困惑したように呟きますが、彼女は何度も卵焼きを指して
「タマゴ!」「タマゴ!」
と叫び続けたのでした……
さて、読者の皆様は既にお気づきかもしれませんが、この2人が衝突してしまった原因は「タマゴ」の脳内イメージにあります。
※ お父様がイメージする「タマゴ」と、お子さんがイメージする「タマゴ」の違い
ゆで卵も目玉焼きも、スクランブルエッグも「タマゴ」だと思っておられるお父様に、卵焼きだけを「タマゴ」だと思っているお子さんが「タマゴ(=卵焼き)」をリクエストし、目玉焼きが出てきたから「コレジャナイ!」と怒っていたわけです。
私たちはしばしば、特定の音の並びを発するお子さんが、ある典型的な状況下でその音の並びを口にするとき、「その言葉が『分かる』のね」と判断してしまいます。
しかし、卵焼きを前にして「タマゴ」という音の並びを発することができるからといって、そのお子さんが大人と同じ「タマゴ」の概念を獲得できているとは限らないのです。
「ほら、青信号だから、渡ろうね」
と親御さんが指をさしたとき、お子さんは信号の横にある青い道路標識を見つめているかもしれません。
「カラスが飛んでるよ」
と空を見上げたとき、お子さんはカラスより遥か上空を飛んでいる飛行機を見つめているかもしれません。
青信号の説明をするときに青信号のイラストを併用したり、カラスの説明をするときにカラスのイラストを併用したりすることは、お子さんが「一般的な言葉の意味」に早く近づくための足掛かりとなります。
■ 海だけど、海じゃなかった
このような「前提のズレによる齟齬」は、お子さんとのコミュニケーションに限った話ではありません。
東大で学ぶために新潟から上京してきた18歳の頃の私は、瀬戸内出身の同級生と、ある有名な短歌の解釈でぶつかりました。
白鳥は哀しからずや 空の青 海のあをにも 染まずただよふ (若山牧水)
互いに「この短歌が好き」と始まった話だったのですが、その先いっこうに噛み合いません。相手の解釈が間違っていると侃々諤々やりあった末、彼が
「なんで、そう思うんじゃろな?」
と私に問いかけて、互いの携帯で海と空の写真を見せ合い、ようやく互いのイメージする「海」と「空」が違っていることに気づきました。
彼は雲一つない空と、キラキラ輝く穏やかな瀬戸内海を想像していて、私は厚い雲に覆われた空と、寒風吹きすさぶ日本海を想像していたのです。
※ 彼がイメージした「海」と、私がイメージした「海」の違い
「空」と「海」。おそらく、どんな子供向け辞書にも載っている基本語彙でしょうし、「空」と「海」の意味を「知らない」と言う大人などいないでしょう。
私たち2人も当然「自分は『空』と『海』の『意味』を『知っている』」と信じ、その前提を疑う必要があるなどとは、思ってもみませんでした。
しかしその実、それぞれが「空」と「海」という言葉で脳内に連想していたものは、結局それまでの人生の、限られた経験に基づく、「ワタシの中の当たり前」でしかなかったのです。
■ 言語による個人の思考の限界を自覚するために、AIの提示するイラストは役立つ
何歳になっても私たちは、「卵焼き」だけを「タマゴ」だと思い込んでいたあの女の子と同じ状況にあり続けます。
「タマゴ」として「卵焼き」だけを出されてきたから「卵焼き」だけが「タマゴ」だと思い、「海」として「日本海」だけを見つめてきたから「日本海」だけを「海」だと思い、「『定型発達』の『健常児』(※この2語の言い回しが好きではないのですが、ここでは説明の簡略化のために使っています)」として過ごしてきたから、「ワタシの見方・感じ方・学び方」だけを「ホモ・サピエンスの見方・感じ方・学び方」だと思いこんで、やり取りしてしまうのです。
彼と私が「海」について衝突していたとき、
「アナタが、おかしい。ワタシが、正しい」
と互いに言葉を強めて主張し合うことは、問題解決に繋がりませんでした。
問題解決に繋がったのは、彼の
「(アナタは)なんで、そう思うんじゃろな?」
という問いかけと、互いに見せ合った携帯の写真――言うなれば「自らの思考の前提となる枠組みを離れ、相手の思考の前提に近づこうとする試み」だったのです。
定型発達の大人と、発達特性をお持ちのお子さんとが衝突したときも、問題解決に繋がるのはきっと
「(アナタは)なんで、そう思うんじゃろな?」
という問いかけ――自らの思考の前提となる枠組みを離れ、相手の思考の前提に近づこうとする試みなのではないでしょうか。
お子さんが言葉で雄弁に語り得ぬ際は、お子さんに代わって「お子さんの脳内はこうなっているかもしれない」と想像させてくれるナニカが、私たちには必要です。
私はそのように人と人との対話を促す代弁者として、「こどもめせん」のAIを発展させていきたいと考えています。
■ お子さんの目線を、想像させてくれるアプリ
少し抽象的な話が続いてしまったので、最後に具体へと戻りましょう。
例えばアプリに「手伝ってよ」と声をかけると、以下のようなヒントが出てきます。
※ 「手伝ってよ」という言葉がけに対応して出る画面
単に「言葉をイラストに変換してくれる」アプリを開発するだけなら、「お手伝い」の場面をひとつ選んで「おてつだい」と字幕をつける方が遥かに容易です。
「お皿を洗っている絵」と「『おてつだい』という平仮名」さえ表示されれば、日本語が当たり前の話し手には「イラストが出てきた! すごい!」と感じていただくことができるでしょう。
しかし、「お皿を洗っている絵」と「意味不明な図形(=平仮名)」を提示されたお子さんが、そこから「お風呂掃除をすればいいのだな」と読み取ることは困難です。
だから「こどもめせん」のAIは、お子さんに代わって「あなたは、何を望んでいるの?」と問いかけてきます。
※ イラストが「出ない」ことに価値がある例
もう一つ、「お魚と卵、どっちがいい?」と問いかけた場面も取り上げてみましょう。
冒頭で説明した通り、当たり前に言語を習得し、当たり前に言語で思考している私たち大人にとって、「卵焼きだけでなく、ゆで卵も目玉焼きもスクランブルエッグも『タマゴ』と呼ぶ不思議さ」を、あらためて自覚することは困難です。
そこで「こどもめせん」のAIは、お子さんに代わって
「あなたが今、脳内にイメージしている『お魚』って何? 『卵』って何?」
と問いかけてきます。「お魚」や「卵」を1枚のイラストに代表させることなく、必要に応じて1つの音声に多数の具象を紐づけ、出てきたイラストが自分のイメージに近づくまでスワイプしていくのが、「こどもめせん」を用いた場合のコミュニケーションスタイルです。
※ 「魚」や「卵」をスワイプして選ぶ画面の例
ちなみに、柔軟な解釈が苦手なお子さんの特性をふまえ、前回「卵」と言ったときに「ゆで卵」のイラストを選んだ端末では、次に「卵」と言ったときにも「ゆで卵」を第一に表示するようプログラムしています。
■ アナタの目線に、ワタシが近づくために
長くなりましたので、まとめますと、
「日本語で思考し、空気を読んで音声を柔軟に解釈し、一度にたくさんのことを記憶できて当たり前の大人」が、
「日本語が苦手で、空気を読めず音声を字義どおりに解釈し、一度にたくさんのことを言われると混乱してしまうお子さん」と向き合うとき、
必要なのは「日本語を離れ、自らの思考の枠組みを離れ、『アナタの頭の中では、ワタシの言葉がけで今、こういうイメージが呼び起されているのかもしれない……』と、想像を促すような仕組み」です。
そのために、いわば「お子さんの目線のシミュレーター」として開発したAIが、この「こどもめせん」なのです。
生まれ持った得意不得意も、過去の様々な経験も、それぞれの言葉で呼び起こされるひとつひとつのイメージも、全く異なるワタシとアナタ。
そんなワタシとアナタが、目線をよりよく揃えられるよう、AIという第三者の視点で仲立ちすることに、私はとても大きな価値と、可能性があると信じています。
次回はこの話をさらに進め、「私たちが他者の視点へ近づくために必要な『共創するシステム』」について、もう少し詳しく書かせていただければと思います。
◆塙孝哉(はなわたかや)
新潟県立新潟高等学校出身。東京大学医学部医学科卒。小児科専門医。
昼夜逆転・不登校だった弟の一助になればと学部時代に所属した睡眠の研究室で、プログラミングに出会う。以降、東京大学医学部附属病院小児科助教等、小児科医としての臨床業務と、プログラマ・AI研究者としての社会実装活動(IT/AIの強みをいかして医療現場をよりよくする活動)を続け、子どもたちの役に立つ取り組みを加速させるべく、2025年5月に株式会社こどもめせんを創業。本アプリケーションのプログラミングは、今のところ全て自身で行っている。生まれた場所や生まれもった発達特性に関わらず、全ての子どもたちが幸せに生きていける社会の実現が夢。本アプリケーションをその端緒として、応援いただける方々と共に育てていきたいと願っている。


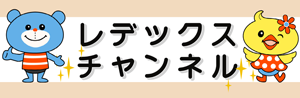
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




