----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■ 連載:子どもに“寄り添う”支援のカタチ―算数学習障害への理解と支援の実践
■□ コラム:映画『教皇選挙』
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第3回 子どもに“寄り添う”支援のカタチ―算数学習障害への理解と支援の実践
───────────────────────────────────…‥・
算数が苦手な子どもたちの中には、単なる「苦手意識」ではなく、発達障害の一つである「算数障害(ディスカルキュリア)」を抱えている場合があります。私は長年、こうした子どもたちの学習支援に携わってきましたが、算数障害の理解と支援には、専門的な知識と丁寧な関わりが必要だと感じています。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:ベネッセ特別協賛シリーズ:特性による学びづらさに寄り添う(最終回)第3回 子どもに“寄り添う”支援のカタチ―算数学習障害への理解と支援の実践
───────────────────────────────────…‥・
算数が苦手な子どもたちの中には、単なる「苦手意識」ではなく、発達障害の一つである「算数障害(ディスカルキュリア)」を抱えている場合があります。私は長年、こうした子どもたちの学習支援に携わってきましたが、算数障害の理解と支援には、専門的な知識と丁寧な関わりが必要だと感じています。
本稿では、算数障害の特徴と、子どもたちに寄り添った学習支援のあり方について、私の研究と実践をもとにお話ししたいと思います。
■算数障害とは
算数障害とは、知的発達に大きな遅れがないにもかかわらず、数の概念や計算、数量の理解などに著しい困難を示す状態です。数の知識、数の操作、数の概念といった算数の基盤となる力がうまく育たないことで、学習に大きなつまずきが生じます。
たとえば、数直線上での位置関係が理解できない、繰り上がり・繰り下がりの計算ができない、文章題の意味がつかめないなど、困難の現れ方は子どもによって異なります。こうした困難は、脳の情報処理の特性に起因するものであり、努力不足や指導の問題ではありません。
■ 一人ひとりに合った支援の大切さ
算数障害のある子どもたちへの支援では、「一人ひとりに合った適切なペースや学習内容を提供すること」が何よりも重要です。子どもたちの認知特性や得意・不得意を丁寧に見極め、それに応じた教材や指導法を工夫することで、学びへの扉が開かれます。
たとえば、ある小学生の事例では、計算はできるのに、文章題になると極端に正答率が下がるという特徴が見られました。この子は、数の操作自体には大きな困難はなかったものの、「文章の中から必要な数値や条件を取り出す」ことが苦手でした。そこで、文章題を図や表に置き換えて視覚的に整理する支援を行ったところ、問題の構造が理解しやすくなり、正答率が向上しました。
また、別の事例では、4+3などの簡単な計算でも指を使って数え続けるお子さんがいました。暗算ができず、数の量感が十分に育っていないため、数直線の課題にもつまずく可能性があります。この場合、「5のまとまり」の理解が重要です。1~3の数は瞬時に個数を把握できる一方で、「5」の理解は自然に身につくものではなく、学習を通じて習得する必要があります。ブロック教材を使って「2と3で5」などの合成・分解を繰り返し確認する支援により、「5のまとまり」の理解と定着が進み、計算にかかる時間が短くなりました。
視覚的な情報処理が得意な子には図や具体物を多用した指導を、聴覚的な理解が強い子には言葉による説明を重視するなど、アプローチを柔軟に変えることが求められます。さらに、手先の操作が苦手な子には、タブレットなどのデジタル教材を活用することで、操作の負担を軽減しながら学習に集中できるようにする工夫も有効です。
また、「できた!」という成功体験を積み重ねることが、子どもたちの自己効力感を高め、学習意欲を引き出す鍵になります。小さな達成感が、次の学びへの意欲につながるのです。支援者は、子どもたちの小さな成長を見逃さず、言葉でしっかりと認め、励ますことが大切です。
■ サポートするうえで大切なポイント
算数の学習支援においては、数の操作や数概念の理解を、具体物と抽象的な数の間を行き来しながら育てていくことが重要です。数は目に見えない抽象的な存在ですが、子どもたちがそれを実感として理解するためには、具体物を使った体験的な学習が欠かせません。
算数は、日常生活の中で使ってこそ意味があります。買い物、時間の管理、料理の分量など、算数の力は生活に密接に関わっています。だからこそ、算数の学びを生活の中で生かせるような支援が必要なのです。
教科書に載っているすべての問題を解けるようにすることが目的ではなく、子どもたちが日常生活の中で算数を活用できるようになることが、支援の本質だと考えています。たとえば、買い物での金額の計算や、おつりの受け取り、時間の読み取りやスケジュールの把握、料理における分量の調整など、生活の中には算数的な思考が必要とされる場面が数多くあります。
こうした場面で困りを感じている子どもに対しては、実際の生活に即した課題を取り上げ、「自分にもできる」「役に立つ」と実感できるような学習機会を提供することが大切です。また、抽象的な数式や計算だけでなく、具体的な場面を想定した問題を通じて、算数が生活とつながっていることを理解させることが、学びへの動機づけにもつながります。
このように、算数を「生活の中で使える力」として育てていく視点が、支援の中核にあるべきだと私は考えています。
■ 教育現場へのメッセージ
教育現場では、算数障害のある子どもたちに対して、「苦手な部分ばかりに注目するのではなく、得意な部分を活かす視点」が求められます。算数が苦手でも、図工や音楽、言語活動などで高い能力を発揮する子どもは少なくありません。そうした強みを活かすことで、学習全体のバランスを取ることができます。
また、教師や保護者が「この子はできるようになる」という信念を持ち、根気強く支援を続けることが、子どもたちの成長に大きな影響を与えます。子どもたちの可能性を信じ、寄り添いながら支援することが、教育の本質だと私は考えています。
■ おわりに
算数障害は、見えにくく誤解されやすい困難の一つです。しかし、適切な理解と支援があれば、子どもたちは自信を持って学びに向かうことができます。
私たち大人にできることは、子どもたちの「わからない」に寄り添い、「わかる」への道筋を一緒に探すことです。算数が「苦手」から「楽しい」へと変わる瞬間を、共に支えていきましょう。
◆熊谷 恵子
筑波大学名誉教授
発達障害の研究(算数、読み書き英語)や学習指導、SST、視覚の過敏症(アーレンシンドローム)、発達障害児の学習支援(特に算数障害/読み書き障害の英語習得)や知能研究(KABC-IIの知能検査の作成とそれを使った支援)などに携わる。株式会社ベネッセコーポレーションが2024年から新しく提供を開始した学習支援サービス〈まるぐランド for HOME〉の監修を務める。
───────────────────────────────────…‥・
■ コラム:本や映画の当事者たち(15) 映画『教皇選挙』 -教皇選挙の舞台裏と内幕を描く、上質な政治ミステリー
───────────────────────────────────…‥・
タイトルからもわかるように、いわゆる障害や病気などの当事者といわれる人たちが描かれている本や映画、DVDなどを紹介します。
今回は、『教皇選挙』(原作はロバート・ハリスによる『Conclave』)について書こうと思います。実際に教皇選挙が行われたというタイミングの良さもあり、3月の公開から今も上映が続いている映画です。第97回アカデミー賞で作品、主演男優、助演女優、脚色など計8部門でノミネートされ、脚色賞を受賞した作品です。
内容は、全世界14億人以上の信徒を誇るキリスト教最大の教派・カトリック教会の最高指導者で、バチカン市国の元首ローマ教皇を決める選挙の舞台裏と内幕に迫ったミステリー。
ローマ教皇が亡くなり、新教皇を決める教皇選挙「コンクラーベ」に世界中から100人を超える候補者たちが集まります。システィーナ礼拝堂の閉ざされた扉の向こうで極秘の投票がスタート。さまざまな陰謀やスキャンダルがうごめく一大イベント。前教皇から依頼され、選挙を執り仕切ることとなったローレンス枢機卿がこの映画の主人公です。「シンドラーのリスト」「イングリッシュ・ペイシェント」の名優レイフ・ファインズが演じます。
私事でありますが、下調べをしていなかった私は、イングリッシュ・ペイシェントで過去大ファンだったレイフ・ファインズだとは気づきもしませんでした。渋い名優だと眺めていました(笑)。月日の経つのは恐ろしいものです。美青年だったかれはすっかり歳を取って、貫禄のある俳優となりました。
レイフ・ファインズを始め、この映画の登場人物はほとんどが老人。地味な印象を持ってしまいがちな映画です。私も硬い映画なのだろうなと思い観たのですが、映画の中の衣裳や建築物、そこにある影や光など、美しく一幅の絵画のようでした。人物の華やかさではなく、世界観そのものが豊かなので、老人ばかりでもひたすら美しく、顔の皺にさえ芸術を感じました。
堅物の映画なのかと思っていると、彼ら彼女(シスター)らの人間くささに驚きます。カトリック教徒の指導者なのに、女性問題や金銭問題、まるで政治家の世界です。それがとてもリアルに描かれます。だから、全く異質の世界ではなく、我々の世界とリンクするのです。上質の政治ミステリーといったらよいでしょうか。
原作は読んでいませんが、主人公の名前・出身地とベニテスの出身地以外は、かなり原作に忠実だそうです。象徴的に出てきていた亀も原作には出てきません。
今回は解説に必要なので、多少のネタバレが含まれます。ご了承ください。
「確信してはいけない」、序盤の演説でローレンスはこう言います。迷い、問い、時に立ち止まりながら、世界を見つめ直す姿勢を持て、ということ。実際、ローレンス自身もまた確信の中にはいなかったのです。彼は信仰に悩み、自らの限界に気づき、辞職すら考えていたのですから。でも、彼は最終的に、その悩みや葛藤の中でこれからも生きていくことを選びます。
大事なところでは、「女性が聖職につく(つまり司祭になる)」ということは、カトリックでは禁忌です。この問題がラストにつながってくるのですが、ちょっとわかりにくいかもしれません。でもココとても重要です。
映画にだけ登場する亀は、卵でいるあいだは性別がなく、雌になるか雄になるかは、環境のさまざまな要素で後から決まるようです。亀は、この映画のテーマを暗示しているのではないでしょうか。
2024年製作/120分/G/アメリカ・イギリス合作
原題または英題:Conclave
エドワード・ベルガー監督
配給:キノフィルムズ
◆はら さちこ
ライター。
編集制作会社にて、書籍や雑誌の制作に携わり、以降フリーランスの編集・ライターとして活動。障害全般、教育福祉分野にかかわる執筆や編集を行う。障害にかかわる本の書評や映画評なども書いている。
主な編著書に、『ADHD、アスペルガー症候群、LDかな?と思ったら…』、『ADHD・アスペ系ママ へんちゃんのポジティブライフ』、『専門キャリアカウンセラーが教える これからの発達障害者「雇用」』、『自閉症スペクトラムの子を育てる家族を理解する 母親・父親・きょうだいの声からわかること』『発達障害のおはなしシリーズ』、『10代からのSDGs-いま、わたしたちにできること』などがある。
■□ あとがき ■□--------------------------


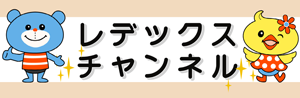
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




