----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
前回から始まったベネッセ特別協賛シリーズの第2回では、読み書き障害研究の第一人者である、小池敏英・東京学芸大学名誉教授によるメッセージをお届けします。
ベネッセは2024年から〈まるぐランド for HOME〉という新しい学習サービスを始めています。そのサービスでは、学びづらさを抱えたお子さまに対して、その子の特性に合わせてタブレット学習とオンライン個別指導を組み合わせた学習支援を行っています。その監修者のお一人が小池先生です。
第2回 子どもに“寄り添う”支援のカタチ―読み書きの困りにデジタルと人の指導で寄り添う
───────────────────────────────────…‥・
私の研究室でLD(学習障害)児の学習支援が依頼されるようになったのは、2000年の頃からでした。知的障害を有する子どもの学習支援を行う中で、読み書きが特に苦手な子どもの支援を依頼されるようになり、読み書き支援について卒論を書くことを希望する学生も多くなりました。2001年は、文部科学省から「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」が出た時なので、時代背景がそのような状況でした。
■ はじめに
■□ 連載:子どもに“寄り添う”支援のカタチ―読み書きの困りにデジタルと人の指導で寄り添う
■□■ 連載:DCDのアセスメント
■□■ 連載:DCDのアセスメント
--------------------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
前回から始まったベネッセ特別協賛シリーズの第2回では、読み書き障害研究の第一人者である、小池敏英・東京学芸大学名誉教授によるメッセージをお届けします。
ベネッセは2024年から〈まるぐランド for HOME〉という新しい学習サービスを始めています。そのサービスでは、学びづらさを抱えたお子さまに対して、その子の特性に合わせてタブレット学習とオンライン個別指導を組み合わせた学習支援を行っています。その監修者のお一人が小池先生です。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:ベネッセ特別協賛シリーズ:特性による学びづらさに寄り添う第2回 子どもに“寄り添う”支援のカタチ―読み書きの困りにデジタルと人の指導で寄り添う
───────────────────────────────────…‥・
私の研究室でLD(学習障害)児の学習支援が依頼されるようになったのは、2000年の頃からでした。知的障害を有する子どもの学習支援を行う中で、読み書きが特に苦手な子どもの支援を依頼されるようになり、読み書き支援について卒論を書くことを希望する学生も多くなりました。2001年は、文部科学省から「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」が出た時なので、時代背景がそのような状況でした。
多くの子どもたちの学習支援を行ってきました。代表的な事例については、著作『イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド』(合同出版)※の中で事例紹介の形で言及しました。著作でも述べている事例を紹介すると共に、開発した支援教材についてご紹介していきます。
※イラストでわかるLD・学習困難の子の読み書きサポートガイド
(A)ひらがな文の流暢な読みが難しい事例
小学校2年生のIさんは友達が多く、昼休みには活発に遊びます。授業のときは、休み時間と比べるととてもおとなしくしています。教科書の音読がとても苦手で、 文章の内容は、友達に教えてもらっているようです。授業中に発言するよう指名されても、言葉で表現することが苦手で、うまく答えを言えないことがあります。 2年生の教科書の中には、「みの回りにいる人」や「ものしりな人」を 「しょうかいする」ことに関係した題材が出てきます。「みの回り」や「ものしり」「しょうかい」などの単語がわからないようでした。また、 「かに」「ふえ」などの2文字単語をうまく読むことができますが、「ふみきり」「ようふく」などの4文字単語については、流暢に読むことができませんでした。そこで、「すいか」「はさみ」などの3文字単語の指導から始めました。
現在、私の研究室では学生による近隣小学校に在籍する児童へのリモート学習支援を行っており、その中では、ひらがな文の流暢な読みスキルを伸ばすことを目的としたアプリ教材を提供しています。
文を流暢に読み進める上で、知っている単語を短時間(約200ミリ秒)に読み取ることが大切です。文章を流暢に読めるようにするためには、単語を短時間で読み取ることができるように支援します。
※図1 ひらがな単語を流暢に読む支援課題
アプリでは、初めに、学ばせる単語を選びます(図1(1))。次いで、正しい単語と一部が誤った単語を呈示し、正しい単語を選ぶように教示します(図1(2))。これにより、単語の全体の形に慣れさせ、目で見てすぐに意味がわかる単語の語彙(視覚性語彙)を増やすように働きかけます。この経験を積むことで、一文字ずつ拾い読みをするのではなく、単語をまとめて読むことができるようにします。
(B)漢字読み困難の事例
前述のIさんは、小学校低学年のときから教科書の音読が苦手で、高学年になり漢字の読みの弱さが特にはっきりしてきました。明るい性格で友達から好かれている彼は、低学年の時には、周りの友達が助けてくれました。今は授業でわからない問題があると、集中が途切れ「わからない」「つまらない」と言い出し、 友達もフォローしにくい雰囲気になっています。
苦手の背景をアセスメントしました。新聞、写真、手紙、道路などの漢字は読めました。イメージが浮かびにくい単語(低心像性単語)については読み間違いが多く、「市立」を「こくりつ」、「地区」を「ちきゅう」と読みました。
日本語の漢字は、複数の読み方を持っているので、新しい漢字単語を読むためには、漢字単語と読みの「言葉」と「意味」や「絵」などをペアで覚える練習(対連合学習)が必要になります。ことばを利用して記憶する力(言語性短期記憶)が弱い子どもは、対連合学習に困難を示します。この場合には、絵を手掛かりとした指導が効果的です。アプリでは、絵を媒介とした指導ができるようにしました。
※図2 漢字単語の読み学習の支援課題
2つの事例で紹介したように、同じように「読み」の弱さを示している子どもでも、必要な指導の内容は千差万別です。
私の研究室におけるリモート支援でも、子どもへの事前アセスメントをベースに指導内容をアレンジするという点と、支援を受ける子どもたちが成長実感を味わえるような仕掛けという点を特に重視して指導役の学生に対してアドバイスしています。
「読み」「書き」に苦手があるLD児は、「なまけている」と誤解されてしまうこともあり、高学年になるにつれ学習への前向きな態度が損なわれがちです。
それぞれの子どもの困りに応じた具体的な支援・指導を実行し、そのうえで合理的配慮も欠かさず行うという周囲のサポートが、子どもの未来を充実させていく手だてとなります。
◆小池 敏英
尚絅学院大学特任教授 東京学芸大学名誉教授。
学習障害児の認知評価と学習支援、発達障害児のコミュニケーション支援に関する研究実績多数。東京都教育委員会『「読めた」「わかった」「できた」読み書きアセスメント』開発に携わる。著書に『LDの子の読み書き支援がわかる本』(2016年, 講談社)など。株式会社ベネッセコーポレーションが2024年から新しく提供を開始した学習支援サービス〈まるぐランド for HOME〉の監修を務める。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:発達障害児の感覚処理・協調運動の問題への支援第5回 DCDのアセスメント
───────────────────────────────────…‥・
協調運動のアセスメントでは観察、子ども・親へのインタビュー、質問紙による検査、個別検査などがあります。それぞれについて説明します。
(1)観察
学校等での観察情報は重要です。体育の時間、机上課題時の姿勢、書字、図工の制作、楽器操作や道具の操作などにおいて協調運動の問題が見られないかを観察したり、情報収集したりすることが必要です。
(2)インタビュー
子どもにはどのようなことで困っているか、どんなことが、どのようにできるようになりたいか、それがどれくらい重要かを確認する必要があります。親御さんにも同様のことを確認する必要があります。医療者が診断をする際などには、周産期の情報や過去の運動発達についても確認します。
(3)質問紙
協調運動の評価には、国際的には協調運動発達に関する質問紙であるDevelopmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-R)が広く用いられており、評価尺度として推奨されています(Blank R et al., 2019)。ただし、このツールは本邦の臨床場面で使用できない状況です。
次に現在、日本で使える評価について説明します。
著者らが作成した3~12歳の子どもの感覚・運動質問紙の協調運動項目(岩永&辻井, 2024a)を用いて日常の協調運動が関係する問題を把握することができます。これは保護者が回答する質問紙で、「姿勢・バランス」、「全身運動」、「手先の運動」、「球技スキル」、「口の運動」の5領域のスコアがパーセンタイル値※で示されます。
※統計用語集
感覚・運動質問紙の協調運動項目(岩永&辻井, 2024a)の質問項目の中で3-6歳の子ども向けの項目についてwebシステム上で回答及び結果表示できるのが、感覚・動作アセスメントKIDSです(岩永, 2023)(※図1)。このシステムを使うことでより簡便に子どもの協調運動の問題が評価できます。
※図1 感覚・動作アセスメントKIDSのアセスメント結果の例
また、小学校の教師が協調運動を評価できるツールとして、感覚・動作アセスメント(岩永, 2019; 岩永, 2024b)があります。これは教師がwebシステムの項目(例:ボタン掛けが上手くできない)に回答することで「書字スキル」、「両側の協調」、「スポーツスキル」、「眼球運動・口腔運動」、「姿勢調整」、「描画スキル」などからなる4領域のスコアがパーセンタイル値で示され、子どもの協調運動の問題がより明確になります。そして、学校での協調運動面への支援内容案が提示されます(※図2)。
※図2 感覚・動作アセスメントの運動面の評価結果の一部
(4)個別式検査
個別式検査では、Movement Assessment Battery for Children第2版(M-ABC2)が多くの国で用いられています。これもエビデンスのある評価尺度として推奨されています(Blank R et al., 2019)。しかし、本邦の臨床現場で使えない状況です。現在、MABC-3日本語版の開発が始まったため、標準化完了後に臨床現場で活用できるようになるでしょう。
本邦で協調運動の評価に使える個別式検査として、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査(JMAP)及び感覚処理・行為機能検査(JPAN)があります。
JMAPは2歳9か月~6歳2か月を対象としており、認知面、言語面以外にバランス、協調運動、運動行為機能を評価する検査を含んでいます。そのため、子どもの運動発達を客観的に評価できます。
感覚処理・行為機能検査JPANは3~10歳の子どもの感覚統合機能をアセスメントするために開発された検査です。JPANでは(1)姿勢・平衡能力、(2)体性感覚識別能力、(3)運動行為機能、(4)視知覚・目と手の協調の4領域のスコアが算出されます。JPANは、多くの運動検査を含んでいるため、協調運動について客観的な評価ができます。
まとめ
DCDのアセスメントについて説明しました。上記の1つではなく、複数の評価方法を用い、それらの情報を統合してアセスメントすることが望ましいでしょう。
文献
Blank R et al.(2019): International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol. 61(3):242-285.
岩永竜一郎・辻井正次編著. 不器用・運動が苦手な子の理解と支援のガイドブック: DCD入門.金子書房. 2024a
岩永竜一郎:感覚・動作アセスメントKIDS.https://www.ledex.co.jp/products/spma-kids.php. 2023
岩永竜一郎:感覚・動作アセスメント. https://www.ledex.co.jp/products/spma1.php. 2019
岩永竜一郎: 増補版 特別支援教育に使える 【感覚+動作アセスメント】マニュアル: 「感覚処理の問題」と「不器用」への対応法. 合同出版. 2024b
◆岩永 竜一郎
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科(保健学科)・作業療法学専攻教授、医学博士、作業療法士、
感覚統合学会理事、特別支援教育士スーパーバイザーほか、長崎県内外のさまざまな委員を兼任。
アスペルガー症候群の息子がおり、長崎県自閉症協会高機能部部長としても活動している。
■□ あとがき ■□--------------------------
次回メルマガは、7月25日(金)の刊行予定です。


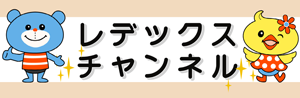
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




