----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■ 連載:アセスメントのその後(最終回)
■□ 連載:報酬改定の影響と「AIセラピストco-mii」
--------------------------------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:読み書きのアセスメントをして子どもの本来の力を発揮する第4回 アセスメントのその後
───────────────────────────────────…‥・
5歳児健診がやっと、各地で試行されてきています。子ども家庭庁の通知に基づいて行うもので、主に発達のばらつきを早期に見つけ、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である5歳児に対して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることとなっています。
特別支援教育の中で一番人数が多いのにまだまだ手薄なLDへの対応が急務です。5歳児健診ではLDは対象になっていません。不登校34万人の中で多くがディスレクシアと考えられます。多くのLD/ディスレクシア児が進路を諦める前に下記のことが必要です。
発達障害の支援を考える議員連盟(野田聖子会長、山本博司事務局長)の総会に訴えました。
上記のような状況下でアセスメントを実施することが急務です。ぜひ、制度化し、政策に組み入れ、予算化をしてほしいです。中でもアセスメントについては下記のような要望を提出しました。
〇アセスメント
学校に入ってから読み書きのアセスメントを全員、または国語下位20%に実施する。(他のASDやADHDの診断の裏で見過ごされている。対応できる医師がいない。診断されても教育でどのようにしたらよいか分からない。)英語圏の多くで実施され、8歳で教育的な診断ができるような仕組みができています。
合理的な変更と調整を実施するにあたり、医療的な診断ではなく教育的なアセスメントが必要です。また、そのアセスメントと読み取り、指導、支援に活かすことができる人員の確保が急務です。教員で賄えないのなら、民間、NPOなどの力を借りるのもあります。
これまで、アセスメントに焦点を当ててお話をしてまいりましたが、大事なのはアセスメントの結果が出てからどうするかです。一人ひとりにあった、適切な読み書きができるようになる方法、アクセスしやすい教材や代替手段、本来の力を測れるような評価などの調整と変更が続かなくてはなりません。そして何より、本人ができる、分かるという実感を持ち自信が持てるようになることが大切です。
最後に効果的なアセスメントを受けて、本来の力を発揮してロールモデルとなってきた若者たちについていくつかお話ししたいと思います。
東京大学でDO-IT※という障害者がICTを使って本来の力を発揮して高等教育に進もうという動きがあり、そのようにして大学に進んでケースはずいぶん増えてきました。とは言っても人口の8%いる中の1000分の1以下だと思われるのですが・・
※DO-IT Japan
エッジではICTに頼るだけではなく、本来の力を発揮する方法をとっており、社会に出て活躍している若者がいっぱい出てきています。
A君、相談があったのは小学校4年生の時、不登校になって保護者は相談に来た。国語の音読がたどたどしく、漢字を覚えない、板書を写すのが間に合わないし、作文や感想文はそっけない。本人は学校のスピードについて行けない自分に嫌気がさして、学校に行きたくなくなっていた。保護者は不登校なので学業に遅れないよう家庭で学校と同じ内容をさせようとしていたが、本人は泣きながら抵抗し、家族関係もぎくしゃくしてきた。アセスメントの結果は読み書きの流暢性も正確性も低くて、音声で聞くと分かり易いことが分かった。
好きなことは昆虫だけだとあったので、せっかく不登校をしているのならと地元の大学の昆虫研究会に出入りさせてもらったり、博物館の昆虫研究会に入ったりしていたら、高校生になって、その地域でいないはずの虫を発見して、表彰された。そうなると学術名を覚えるのに英語も身につき、やる気も出て、地域の国立大学に現役で入ることができた。今は研究者の道を進んでいる。
ここで私たちが学べるのは、「興味がある」「好き」「面白い」を切り口に、背景知識をいっぱい蓄え、多感覚の体験を積んだ結果です。また、アセスメントをして、メタ認知が育ち、自分に合った学習方法に巡り合うことができたことです。異年齢のメンター的な存在も忘れてはならないでしょう。何よりも本人が没頭できることを貫けたことが要因だと思います。
アセスメントを受けて、伝統芸能の道に進んだのが、鏡味仙成さんです。自分でよく考え、中学校で学校の勉強は終わりにして、芸の道に進みました。体で表現する能力がものすごく高いのです。師匠の扉をたたき、中卒の弟子は取らないと言われていたのを、通いつめ、ついに異例の弟子となり、20歳にして真打になりプロとして独り立ちをしています。彼の芸はほれぼれするくらいカッコイイし、口上も歯切れよく、心地よい。最近では同じくディスレクシアの落語家柳家花緑さんと共演することもあるようです。
近頃では大人になってからのアセスメントも行っています。仕事上必要な資格試験が間に合わず何回受けても通らないというので相談を受けました。幸い、診断基準に「限局性学習症」が入ったので、大人のディスレクシアの診断を出せるようになり、当法人でとったアセスメントの結果の読み書きの流暢性が顕著に低いという結果を参照に診断を受け、資格試験で「時間延長」の配慮(変更と調整)を受け、見事に受かり、昇進が叶いました。
アセスメントをしていてびっくりするのが、大人になっても流暢さはさほど改善しないということです。読みも書きもすらすらとはなかなかなりません。私自身も講演をしたり、通訳をしたりできるが、原稿を渡されると身動きが取れなくなり、しどろもどろで間違えだらけになってしまうのです。その代わりに、体験やいろいろな媒体を使って背景知識を蓄え、自分の考えをまとめることで、長文読解は問題なくできるし、PCを使って修士論文を書くこともできます。
◆藤堂栄子(Eiko Todo)
認定NPO法人エッジ 会長 (NPO EDGE Japan Dyslexia Society)
NPO法人エッジエッジは読み書きの困難を持つディスレクシアの人たちが本来の力を発揮し活き活きと暮らせる社会を目指して活動をして21年になります。これまでの活動は皆様のご支援、お力添えによって実施、継続をすることができました。今後も活動をより多くの方に届けられますように、皆様のご寄付をお願いいたします。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載「AIセラピストco-mii」がつくる発達支援の未来第2回 報酬改定の影響と「AIセラピストco-mii」
───────────────────────────────────…‥・
1.報酬改定が放課後等デイサービスに与える影響
この改定の背景には、短時間の利用ニーズへの対応と、支援の質向上を目指す目的があると思います。そのため、単純に支援時間を増やすだけでなく、適切な支援の提供と加算の活用を通じた収益確保が求められています。
このような状況において、安定した事業所運営を続けていくためには、加算を最大限に活用する必要があると考えています。特に「専門的支援体制加算」「専門的支援実施加算」の2つは、経営の安定化(収益性)と支援の質向上の両面で重要な役割を担っており、多くの事業所が取得を目指すべき加算です。
2.専門的支援実施加算とは?
専門的支援実施加算は、専門職による計画的な支援を行うことで取得可能な加算です。この加算を取得することで、1回の支援あたり150単位が加算され、最大で月6回まで算定が可能です。専門的支援実施加算を算定することができれば、事業所の収益向上が見込めるだけでなく、専門性の高い支援を行うことが可能です。
しかし、この加算を取得するためには「専門的支援実施計画書」の作成が必須となります。この計画書は、子どもの発達状況や支援の必要性を的確に評価し、専門的な支援計画を策定するものですが、その作成には高い専門性が必要なだけでなく、多くの事務作業時間を要します。そのため、多くの事業所では「加算を取りたいが、計画書作成の難易度が高く負担が大きい」という課題を抱えています。
こうした課題を解決するために、AIセラピストco-miiは専門的支援実施計画書の作成をサポートする機能を搭載しています。次のセクションでは、この機能がどのように事業所の負担を軽減し、加算取得を支援するのかを詳しくご紹介します。
3.AIセラピストco-miiで専門的支援実施加算を取得
(1) co-miiの専門的支援実施計画書作成機能
co-miiには、専門的支援実施計画書を自動出力する機能が搭載されています。アセスメント結果をもとに、必要な支援領域を特定した上で、適切な計画書を提案します。
計画書の作成では、根拠となるデータをもとに、個別の支援方針を明確化。さらに、国が定める専門的支援実施加算の要件を満たした形式で出力されるため、書類の不備による加算申請のミスも防ぐことができます。
この機能により、事業所のスタッフは本来の支援業務により集中できるようになり、計画書作成にかかる負担を大幅に軽減できます。次に、この機能を活用することで具体的にどのようなメリットが得られるのかを解説します。
(2) co-miiの活用によるメリット
co-miiを導入することで、事業所は次のようなメリットを得ることができます。
・事務作業の負担軽減:計画書の作成時間が短縮され、スタッフが直接支援に充てられる時間が増える。
・加算の適正取得:専門的支援実施計画書の内容が統一され、適正な加算取得が可能になる。
支援の質向上:専門家の知見に基づいたアセスメントを活用し、科学的根拠に基づいた支援計画を作成できる。
・保護者との信頼関係強化:データに基づく説明ができるため、支援内容の透明性が向上し、保護者の理解と納得を得やすくなる。
このように、co-miiは「収益を確保しながら、業務負担を軽減し、質の高い支援を実現する」という事業所の課題を解決するツールとして、多くの現場で活用されています。
※co-mii資料イメージ
次に、実際にco-miiを導入した事業所の声を紹介します。
4.co-mii導入事例
・放課後等デイサービス「ひかりのにわ」
「今まで、「個別支援計画書」の作成は児童発達管理責任者の個々の能力差が出ていましたが、一定の水準で作れるようになりました。あいまいな評価に基づかず、根拠あるアセスメントと評価を実施できるようになったので、事業所の水準を維持しやすくなっています。」
・「めいめい」施設のスタッフの声
「提示課題に必ず目的、ねらいがあるため、実際に支援していても迷うことなく支援ができると感じた。また、アセスメントの診断結果を見ながら、保護者と困りごとの共有ができるため、対応しているスタッフも共感性が高まり、保護者とのコミュニケーションが初回から密にとれるようになりました。」
5.まとめと今後の展望
報酬改定により、放課後等デイサービスの収益構造は大きく変化しました。加算の活用がより重要になる中で、co-miiは専門的支援実施計画書の作成をサポートし、事業所の収益向上と支援の質向上を両立できると考えています。これからも、支援現場の負担軽減と質の向上に貢献できるよう、さらなる機能強化を進めていきます。
「AIセラピストco-mii」について詳しくはコチラ
次回予告
次回のメルマガは、「AIセラピストco-mii」を徹底解剖!支援現場での活用法をお送りします。AIセラピストco-miiについて、より詳細に機能の紹介をさせていただく予定ですので、ここまでの記事で少しでも気になられている方はぜひご覧ください!
◆中村 一彰
株式会社ヴィリング 代表取締役
STEAM教育スクール「STEMON(ステモン)」、放課後等サービス向け療育教材「すてむぼっくす」、発達障害AIアセスメント「co-mii」、バイリンガル英語家庭教師「お迎えシスター」などを運営。著書『AI時代に輝く子ども』『放課後等デイサービス 5領域に対応療育トレーニング50』
所属学会:日本LD学会、日本授業UD学会
◆小嶺 一寿
AIセラピストco-mii 開発者
株式会社みやとの作業療法士。療育センターや福祉の児童分野で16年以上の経験。著書『放課後等デイサービス 5領域に対応療育トレーニング50』
※AIセラピストco-miiとは
AIセラピストco-miiは、児童発達支援事業所や放課後等デイサービス向けの支援システムです。
5領域に対応した「アセスメント」の実施
「個別支援計画書」の半自動作成
アセスメント結果に基づいた「療育メニューの提案」
「専門的支援計画書」の半自動作成
これにより、支援の質を向上させるとともに、業務の効率化にも貢献します。
詳しくはコチラ
お問い合わせ先 TEL:03-5303-9850 MAIL:sales@viling.co.jp
4月23日にHUG特別オンラインセミナー 子どもたちを知るシリーズ第1回「感覚の困りとは?」が岩永竜一郎・長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授を講師として実施されました。参加は200名以上でした。
第2回は本メルマガ編集長の五藤が「認知機能とは?」と題して5月20日に行います。よろしければご参加ください。
次回メルマガは、連休明けの5月16日の予定です。
▼YouTube動画 レデックス チャンネル ▼
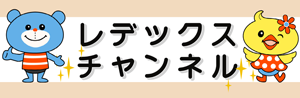
第2回は本メルマガ編集長の五藤が「認知機能とは?」と題して5月20日に行います。よろしければご参加ください。
次回メルマガは、連休明けの5月16日の予定です。
▼YouTube動画 レデックス チャンネル ▼
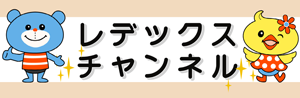


 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




