----TOPIC----------------------------------------------------------------------------------------
■ 連載:ミシガン大学リハビリテーション見聞録3(最終回)
■□ 連載:発達障害と依存症の関係について
--------------------------------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:小児リハビリテーションを学びたい!若手リハ医の奮闘記
第4回 ミシガン大学リハビリテーション見聞録3(最終回)
───────────────────────────────────…‥・
今回は、2021年4月から2023年3月までの約2年間にわたって経験したミシガン大学でのリハビリテーション留学生活の最終回です。ここでは、私が取り組んだ研究、アメリカの精神、そして恩師であるDr.Hurvitzとのやりとりを通じて学んだリハビリテーション科医としての心得についてお話しします。
〇雪舞う異国で芽生えた研究心
正直なところ、留学前の私は研究とは無縁でした。研究は一部の頭の良い人がやるものだと思い込んでいましたし、コーヒーの存在を知らない人がコーヒーを飲みたいと思わないように、自分から研究に挑戦するという考えはまったくありませんでした。しかし、ミシガン大学リハビリテーション科の教授であるDr.Hurvitzに、「せっかく留学するなら研究もやってみたら?」と声をかけられ、研究を始めることになりました。
とはいえ、学生時代の英語の成績は常に平均以下、留学当初はスーパーでの買い物も苦労する状態でした。最初の研究ミーティングでは、エレンという研究アシスタントとDr.Hurvitzが参加していたのですが、内容の30%も理解できず、とにかく元気に返事をすることだけを心がけました。その後、握力計や同意書などの研究道具を駐車場まで運ぶことに。Dr.Hurvitzに「君の車はどこ?」と聞かれ、「車?運転免許すら持っていません!」と答えたところ、どうやら私がクリニックに道具を運ぶ役割だったようです。4月のミシガンで、雪が舞う寒空の下、Dr. Hurvitzの呆気にとられた表情は今でも忘れられません。このように研究生活は波乱の幕開けでしたが、参加者集めから論文執筆まで、本当に多くの学びがありました。
〇握力は全身筋力や健康のパラメーター
私が取り組んだ研究テーマは、脳性麻痺やダウン症、二分脊椎といった小児期発症の障害を持つ患者さんの握力を調べることでした。握力計測にはどんなメリットがあるのでしょうか?
一般成人では握力が全身の筋力と相関することが知られています。一方、小児期発症の障害を持つ患者さんは体組成が異なり、全身の筋肉量を予測するのは簡単ではありません。そこで、もし障害がある方にも握力と体組成(筋肉量や体脂肪率)の関係があることがわかれば、診察室やリハビリテーションの現場で握力を測るだけで筋肉量を予測できる可能性が出てきます。さらに、握力は生活習慣病リスクの予測にも役立つとされており、障害を持つ方にもこの関連性が確認できれば、生活習慣病リスクの高い患者さんへの有用な指標となるかもしれません。
最終的には、脳性麻痺を持つ18歳以上の方に焦点を当てて研究を進めました。その結果、脳性麻痺を持つ成人でも握力が体組成と相関し、GMFCS(脳性麻痺の重症度分類)単独よりも、握力を組み合わせた方が将来の生活習慣病リスクをより正確に予測できることがわかりました。さらなる研究が必要ですが、この研究が脳性麻痺の方の健康増進に役立つ可能性があると自負しています。
興味のある方は、以下のリンクから原文をご覧ください。
原文はこちら>>
研究データを集めるために外来を見学させてもらいながら、1人1人の患者さんに研究参加を呼びかけたのですが、驚くべきことに参加率98.2%と声をかけたほぼ全員が研究に参加して下さいました。侵襲的な検査ではありませんがアンケートも含めるとそれなりの時間を要し手間には違いない中、100名を超えるたくさんの方に参加してもらえたことにアメリカに根付く人助け精神を感じました。また特に重症脳性麻痺を持つご本人や親御さんから「研究に参加することであなたや誰かの役に立てたならこちらこそ嬉しい」といった言葉を多く頂きました。同じ研究チームの他の医師からも「この研究の素晴らしいところは、重症の脳性麻痺の人たちを除外せず研究に含めたところですね。コミュニケーションに困難がある患者さん達を扱った研究はとても少ないですから。」とコメントをもらったのも印象的でした。
Dr.Hurvitzとこんな話をしたことを覚えています。「最近、ダウン症のアイドルが注目されているよね。障害を持ちながら輝くのは素晴らしいけれど、すべての人がアイドルになれるわけじゃないし、障害があるからといって特別なことをしなければならないわけでもない。存在しているだけで十分、誰かの役に立っているんだから。」
私たちの研究は大規模で輝かしいスポットライトを浴びるものではないかもしれませんが、もしこの研究が誰かの役に立ち、参加してくれた方々の「誰かのために」という思いに応えられたのなら、研究者としてこれ以上の喜びはありません。参加者の笑顔を思い出しながら、心からそう感じています。
アメリカで感じたもう一つの特徴は、寄付文化です。日本ではお菓子などをお礼にいただくことがありますが(お気持ちだけでお断りしておりますが)、アメリカでは「お世話になったので、研究に寄付したい」という方が多くいました。数十ドルの寄付であっても、その精神にアメリカらしさを感じました。また研究を行う際においても、とにかくグラント(研究資金)を獲ることを求められるのですが、その多くが企業や法人あるいは個人からの寄付によって支えられています。研究会においても医療関係者だけでなく様々な法人や企業が参加し、研究者とグラントの交渉をしたり、研究経過についても活発な議論が交わされたりしていました。寄付文化が、アメリカが世界トップクラスの研究大国である要因の一つだと実感したエピソードでした。
〇Dr.Hurvitzから学んだリハビリテーション科医としての心
2年間という短い間でしたが、Dr.Hurvitzの外来を見学し、研究について議論を交わす中で、数え切れないほど多くのことを学びました。多くの素晴らしい言葉をいただきましたが、特に印象に残っているのは、患者さんに喜んでもらえた時や良い治療につながった時、また研究のデータ解析中に興味深い事実が見つかった時などに、Dr.Hurvitzがいつも「だから、臨床も研究もおもしろいんだ。やめられないね!」と、とびきりの笑顔で言っていたことです。彼は今年2月に主任教授を引退されましたが、今でも研究を通じて連絡を取らせてもらっています。Dr.Hurvitzをはじめとする多くの先生方や患者さんから学んだことは、私のリハビリテーション科医としての根幹を形成し、今後も生き続けるでしょう。
最終回ということもあり、個人的な内容が多くなりましたが、少しでもミシガン大学での留学生活を感じていただけたなら幸いです。拙い文章にもかかわらず、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
※美しいミシガン湖
◆杉山 智子
昭和大学江東豊洲病院リハビリテーション科助教
医師の初期研修終了後、燃え尽き症候となり沖縄三線を片手に放浪。美容皮膚科医等を経て、自分が目指していた医師像「障害のある方の人生に寄り添いたい!」を思い出し、昭和大学リハビリテーション医学講座に入局。
2021年よりミシガン大学で小児リハビリテーション医学を学ぶ。
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:発達障害と依存症
第2回 発達障害と依存症の関係について
───────────────────────────────────…‥・
〇注意欠如多動症と依存症
成人期ADHDの世界規模の疫学調査では、ADHDがある人の少なくとも9人に一人に物質使用症(アルコール依存症や薬物依存症など)がみられ、また物質使用症の8人に一人にADHDがみられたことが報告されています。その他にもギャンブル行動症(ギャンブル依存症)とADHD、インターネットへの嗜癖とADHD、ゲームへの嗜癖とADHDなど、様々な依存症/行動嗜癖との関連が報告されています。
ADHDがある人は計画的に何かをやるのが苦手で、まっすぐ家に帰ろうと思ってもついつい居酒屋やパチンコ店に寄り路をしたり、仕事や課題をやろうとしても、すぐに脱線して、気づいたらスマートフォンでゲームやネットサーフィンをしたり、という人は多いと思います。このような脱線のしやすさが依存症の始まりとなることもあります。
またADHDと依存症の脳機能の問題で、共通するキーワードとして挙げられるのが、「報酬系の障害」です。ADHDがある人は狩猟民族の子孫ともたとえられるように、後先を考えずに、目の前にある報酬、リスクのある刺激に飛びついてしまう傾向があると言われています。アルコールや薬物などの物質や、ギャンブルやゲームなど行動に、強い刺激を感じると、それにはまってしまい、過剰にのめりこんでしまうことあります。このような刺激の強い報酬に反応しやすい傾向が依存症の発症に影響していることが想定されています。
〇自閉スペクトラム症と依存症
自閉スペクトラム症(ASD)は社会的コミュニケーション・相互的社会的関係の問題と、行動や思考の限局的・反復的で柔軟性のないパターンの2つの軸で評価される発達障害の一つです。ASDは、一般人口の1-2%に存在すると考えられており、最近では36人にひとり、という報告もあります。社会的コミュニケーションの問題として、「言語的/非言語的な社会的コミュニケーションの理解が困難」、「他者の気持ちを想像し、それに応える能力の問題」、「仲間関係を作り、維持する能力の問題」などが挙げられています。限局性・反復性の特徴の中には、「特定のタイプの刺激(インターネット等)や物質への異常に強い没頭」や「感覚刺激に対する過敏または低反応、または感覚刺激に対する異常な関心(音、光、質感、においおよび味覚、熱、寒さ、痛みなど)」などが含まれます。
ASDもADHDほどではないですが、依存症との関連が指摘されています。様々な研究から、ASDがある人のアルコールやニコチン、薬剤への依存、ゲームやインターネットへの嗜癖の度合いは、一般の人よりも高いことが報告されています。
ASDがある人は、社会的コミュニケーションの問題のため、他者とのふれあい/つながりが希薄になってしまう場合があります。このようなときに対人関係から得られない充足感を、ゲームやSNSなどの行為や、アルコールやカフェインなどの物質に求めてしまう状態がみられます。
またASDと依存症との関連は、ASDの限局性・反復性の特徴の中の、刺激や物質に対する没頭や、感覚の問題の一つである「感覚探求」と関係があるのではないかと筆者は推測しています。パチンコやゲームなどの強い光や音から得られる感覚刺激、薬剤やアルコールなどによるハイになったり、沈静化したりする身体感覚に異常なほど惹かれ、のめりこむ状態がみられる場合があります。
〇発達障害と依存症との関係
発達障害では、ADHDもASDも日常的に失敗体験の繰り返しとなる場合があります。その際に、また失敗したらどうしようという不安や上司からの叱責による気分の落ち込みが生じ、これらのネガティブな感情から逃れるために、物質や行為にはまってしまう場合があります。
また発達障害では、場の空気を読まなかったり、後先を考えなかったりする言動が多く、これによって対人トラブルが多くなる傾向があります。このような傾向から、家族や友人からの助言も耳に入らず、依存症の傾向に拍車がかかる場合があります。
以上のように発達障害と依存症は併存することが多いことが最近になって少しずつ明らかになっています。しかし発達障害がある人は、従来の依存症治療の中心となる集団療法や、アルコールでの断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス「無名のアルコール依存症たち」)などの自助グループになじまず、治療のレールに乗れないことが多いように思います。次回はこのようなタイプの人の支援・治療についてお話をしたいと思います。
◆今村 明
長崎大学生命医科学域 保健学系作業療法学分野
長崎大学子どもの心の医療・教育センター
■□ あとがき ■□--------------------------
次回は、年明け1月10日(金)に刊行します。
読者の皆様、今年1年本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございました。次回は、年明け1月10日(金)に刊行します。
どうかよいお年をお迎えください。


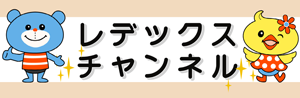
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




