■ 新連載:教育あるある話~元小学校教員の大学教授がつぶやく現場の話~
■□ 連載:「疲れやすい」ってどういうこと?~当事者の視点~
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
■□ はじめに ■□--------------------------
今回から始まる連載をご紹介させていただきます。
寄稿者の増本利信先生については、2011年6月に増本先生の勉強会でのご講演を、許可をいただいて編者がレポートした3回の連載があります。
増本先生は長崎県で小学校や特別支援学校の教員を30年間勤められ、現在は熊本にある九州ルーテル学院大学で教員養成に携わっておられます。
学校時代は通常学級から始まり、情緒・知的・肢体不自由の支援学級やLD/ADHD等通級指導教室の担任をご経験されています。ご本人によれば、子どもたちから学んだことをベースに、次世代の教員を育てるのに活かしたいとのことです。
今回の連載では、学校時代に出会った子どもたちのエピソードや、特別支援教育コーディネーターとして取り組んだこと、現在担当している大学生に思うことなどをご紹介していただきます。肩の力を抜いて、「あるある」と思っていただきたいとのご希望です。
───────────────────────────────────…‥・
■ 新連載:教育あるある話~元小学校教員の大学教授がつぶやく現場の話~第1回 見たて違いが大違い、あるあるな大失敗。
───────────────────────────────────…‥・
これまでたくさんの子どもたちと学んできました。今回はその中で見立てや関わりがうまくできずに教師も子どもも苦しんだ経験を 3つ挙げてみます。
1.こだわりすぎたのは誰だ
多良美さんは当初小学校中学年の女児、私は通級教室担当者として週に2時間の個別指導で関わりました。
担任や保護者からオーダーがあったのは「計算技能の向上」で一致していたので、個別の指導計画の目標もそこにおいていました。
足し算や引き算はワーキングメモリをサポートするためにさくらんぼ計算※で、掛け算や割り算はマス目シートを使って不器用さや視覚認知に配慮してなどと考えながら課題に取り組ませていました。
※編集部注:さくらんぼ計算
さくらんぼ計算とは、1つの数字を2つに分解して計算する方法で、小学校1年生が繰り上がりの足し算や繰り下がりの引き算を習う際に登場します。計算をする際に使われる図がさくらんぼの形に似ていることから「さくらんぼ計算」と呼ばれています。
毎時間毎時間、指導の中の1パートとして計算を繰り返しました。
なんと4年間も!
卒業を控えたある日お母さんから言われました。
「先生、多良美は6年生になって、お店で複数のお菓子を買った時、いくらぐらい出せばいいのかわからないんですよ。」
多良美さんは確かに繰り下がりや繰り上がりの計算技能は高まったかもしれません。しかしながら、冷静に考えるとこれまで行ってきた計算学習に何の意味があったのかわからなくなりました。
もちろん手順良く計算できることはマイナスではないのですが、数の大小関係を把握することや見積もりを立てることなど、日常生活に生きる数概念を育てていくこと、計算機などのツールを利用するスキルを習熟させることも重視すべきだったのだと振り返ります。
計算さえできるようになれば、とこだわっていたことが恥ずかしく思い出されます。
2.口約束は互いを混乱させる
長代さんは高学年男児、行動の問題が強く情緒・自閉症学級の在籍となりました。
知的発達は非常に高いものの、他児とのコミュニケーションを適切に紡ぐことが難しく様々な場面でトラブルが見られました。教師に対しても非常に馴れ馴れしく関わる反面、思いが遂げられなかったり、修正を求められたりした場面となると極度に不安定となり、怒りを強く見せる姿が見られました。
新設された支援学級で担任となった私は、長代さんと協力し、話し合いながら学級づくりをしていきたいと考えました。
そのため、大まかな方針は立てたものの、詳細はその場その場で長代さんとともに考え、よりよくしていこうと伝えました。
滑り出しも良く、いい学級になりそうだと思ったのもつかの間で、1ヶ月もすると長代さんの行動や情緒が不安定となっていきました。
あの頃、泣き叫びながら長代さんが口にしていたのは、「話し合いながら進めるって言ったじゃないか」「前の時言っていたことと違うじゃないか」ということでした。
私は長代さんとできるだけたくさんのことを考え、互いに折り合いをつけながら生活ルールを考えていきたいと思いました。が、その前提にあるのは「学校のルールや社会生活上のルールに則る」ということであり、話し合うということは「互いの意見をすり合わせる」ということであることをしっかりと確認できていなかったのです。
加えて、不安定な状態で興奮している長代さんに対して私が過度に関わったり、要求を譲歩したりしたことも拍車をかけました。
これらの行動を引き起こした理由は、事前の確認がぼんやりとしており、誤解や曲解を生み出す要素が大きかったこと。一つ一つの判断に差異があり、いわば口約束同然となったことで長代さんが混乱したことが挙げられます。
翌学期からは、学級づくりについて骨組みをプリントで明確にして、互いに確認した上で学習を始めました。また、改善のためにすり合わせたことは学級ルールブックに明文化し、判断に困った時はそれを参照するように徹底したことにより、この件に関する不安定な言動は見られなくなりました。
3.感覚の過敏さへの配慮は慎重に
感覚が過敏な児童と出会うことがあります。特定の肌触りや匂い、音など様々な要素で好みがあり、児童によっては嫌悪感を強く見せることがあります。
通級指導教室で関わっていた時二さんは広汎性発達障害診断のある高学年の男児です。
皮膚の感覚が鋭く、ネバネバしたりどろっとしたりしたものをとても苦手にしていました。
高学年の仕事にプール掃除があります。時二さんも学級のみんなと参加することになりました。
当初の計画では時二さんはプールサイドや更衣室など汚泥を触らずにできる仕事を割り当てるようにしていました。
多くの子どもたちにとってプール掃除は泥だらけになりながらも学級のみんなとともに水浸しになりながら頑張って楽しくやり遂げることのできる達成感の強い活動です。そこで私はなんとか時二さんが共にプール内の掃除ができないかと考えました。
思いついたのは長靴に雨合羽、マスク着用など皮膚を露出しない完全防備体制での参加でした。
時二さんもまんざらでなく、当日の掃除も楽しく参加してくれました。よしよしと我々も喜んでいたのですが、その後実際のプールでの水泳学習に時二さんは一度も参加できないという状態になりました。
理由を紐解いていくと汚泥の見た目と臭いをプールに行くたびに思い出し吐き気をもよおすとのことです。過敏さは触覚過敏だけにあらず、また自閉圏の方がよく見せるフラッシュバックの強さを配慮していなかった私の完全な誤対応でした。
4.まとめにかえて
子どもの困りを見立てて、適切に関わることを教師は意図しています。が、時にその見立てが一方的であったり、一部分しか見ていなかったりすることで、子どもとすれ違うことが少なくありません。「〇〇に違いない」「きっと〇〇だろう」と先入観や思い込みを持たず、客観的に幅広く児童生徒の心を汲み取ることが大切だなと痛感しています、
◆増本利信(ますもと・としのぶ)
九州ルーテル学院大学大学院人文学研究科教授/学長補佐
日本LD学会常任理事/特別支援教育士資格認定協会理事
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:あまり知られていない発達障害のある人の疲労について 第3回 「疲れやすい」ってどういうこと?~当事者の視点~
───────────────────────────────────…‥・
レデマガ読者の皆様、こんにちは。筑波大学の仲田真理子です。連載「発達障害と疲労」、第2回ではASDのある人の疲労と、発達障害における疲労の生物学的背景についての仮説をご紹介しました。第3回では、疲れやすい特性をもつ発達障害の人はどのような実感を持って暮らしているのかを、私の体験をベースにご紹介したいと思います。
私は1986年に生まれました。子どものころは発達障害の診断はついていませんでしたが、そのころから自分はいろいろなことができないと感じていました。本を読むのは好きでしたが、それ以外のすべてのことは「今これをやらなかったら死んでしまう」ぐらいの気持ちになるまで自分を追い詰め、とても気合を入れないと取り掛かることができませんでした。
特に文字を書くことが苦手で、鉛筆で文字を書いていると、頭の内側を金だわしでこすられているような独特の不快感があり「一刻も早くやめたい」ということ以外何も考えられなくなりました。
2005年に大学に入学して一人暮らしが始まると、学生宿舎の5畳の自室はたった数か月でゴミ屋敷になりました。夜9時にサークルが終わって帰宅してから夕食を食べるだけで12時を回ってしまい、生活も勉強もうまくいきませんでした。
幸い、同じ状況ではないにせよあまり優等生ではない(※当時)仲間がいたので「うちら、ダメ人間だよねー(笑)」と言いながらそれなりに楽しく暮らしてはいました。「今これやらなきゃ死ぬ」を発動し続けた大学2年生の終わり、ついに大きく調子を崩して、精神科への通院が始まりました。
その後紆余曲折を経て、大学院生の私はついに発達障害の診断を受けて、ADHDの薬である「ストラテラ(一般名アトモキセチン)」を飲むことになりました。すると、世界が変わりました。「今これやらなきゃ死ぬ」と思わなくても、色々なことができるようになったのです。
毎日、午前中に学校に行けるようになり、講義や打ち合わせのときも、メモを取りながら最後まで座っていられるようになりましたし、1本のゲームソフトを最後まで遊ぶことができたときは、とても感動しました。
ちなみに、動物実験では、アトモキセチンはノルアドレナリンを増やすことで脳内の炎症を抑える作用があることが報告されています(O'Sullivan et al., 2009, 疲労と炎症については第2回参照)。
なんとか大学院を修了して研究所で働いているうちに、疲労の定義を知りました。「独特の不快感」「今やっている活動を行いたくない、続けたくないという経験」。
全ての作業を「一刻も早くやめたい」と思いながらやってきた自分。大変そうな作業を先延ばしにし続けて、締め切りを守れないことが多かった自分。「努力のできない子ども」だと言われ続けた自分。
これまで、何かができないときは自分自身でも「面倒くさい」とか「やる気が出ない」とか「気分が落ち込んでいる」ことが理由だと思ってきました。でも、それってもしかして疲労なんじゃないだろうか。
「発達障害 疲労」で検索をかけて、発達障害のある人の疲労に関する研究がほとんどないことに驚きました。これまで自分の「できないこと」をずっと認知、感覚の問題、トラウマなどの視点から理解しようとしていましたが、疲労という視点は、私の様々な困りごとのなかでこれまで説明できなかった部分を、うまく説明してくれるような気がしました。
ここでhappy endといきたいのですが、第1回、第2回を読んでくださった読者の皆様はご存じのように、残念ながらそうではありません。発達障害と疲労をめぐる謎解きは、まだ始まったばかりです。
そこで今回は、発達障害当事者の視点から、研究者や支援者の皆さんにも注目してほしいなと思う、これまでの記事で取り上げられなかった2つのポイントについて書いてみたいと思います。
(1)疲れやすいことを隠すストレスは大きい
これまでの連載では、疲労感の強さや、その生物学的背景をテーマにした研究を取り上げてきました。このような疲労そのものについての研究に加えて、「疲労の意味(meaning of fatigue)」をテーマにした一連の研究があります。要するに、疲れるということは、主観的にどのような経験であるか、という研究です。
これまで、身体的疾患があって、疲れやすい人を対象にしたインタビュー調査が行われてきました。それらの研究からは、慢性腎臓病や関節リウマチなど、疲れやすい疾患のある人々が「疲れすぎることに罪悪感を感じる」(Primdahl et al., 2019)「自分の疲れ方は正常ではないと思う」「疲れていることを周りの人に信じてもらえない」(Jaime-Lara et al., 2020をもとに仲田・上地、2024が作成)など、疲れ方が多数派の人とは違うことに対して、ネガティブな感情を抱かざるを得ない現状が浮き彫りになっています。そして、マイノリティーであることが大きなストレスになることは、すでによく知られています(Frost & Mayer, 2023)。このようなネガティブな感情の報告は、疲労そのものに加えて、周りの多くの人に比べて自分が疲れやすい事実、つまり「疲労におけるマイノリティー」であることがストレスとなっていることを示唆するものであると考えています。
私自身も、疲れやすいことによって社会的信用が低下するのではないか、という不安に日々おびえながら生きています。実際に仕事に割ける時間が短い、ということに加え、作業と作業の合間に他の人より多く休憩が必要であることが、理解されないのではないかと不安です。同じ6時間の作業をするのでも、健常者の想定したスケジュールは3時間働いて1時間休憩し、また3時間働く、というものですが、私はそれでは体力・気力がもちません。1時間半作業して1時間から1時間半休む、というのを4回繰り返すのが、おそらく私にとって一番成果を出せる働き方ですが、ほとんどの職場の勤怠管理システムはそのような働き方には対応していないでしょう。
また、体調を崩した後復帰できるようになるまでの期間も、私はまわりの他の人よりも長いような気がしています。まわりに頑健な人が多い環境で生きてきたため「サボっている」と思われるのではないかと思うと怖くて、本当に起き上がれないレベルの体調不良でない限りは、痛みなどを無視して活動する習慣がついてしまいました。とはいえ、自分が10代、20代のころは、周りの人も若かったため、身体がいうことを聞かないということ自体を信じてもらえないこともありましたが、今では周りの人も年を取ってだいぶ理解してもらいやすくなった気がします。
このような疲れやすい体質に生まれて、悪いことばかりではないかと思う方もいるかもしれませんが、私たちも取り組んでいる「疲労の意味」研究の結果を見ると、どうも悪いことばかりではないようです。精神疾患のない人は、全体としてみたときに疲労感が強いと「自分ならできる」という感覚が弱い、すなわち「自己効力感」が低い傾向があるのですが、そのような傾向は精神疾患のある人ではみられませんでした(仲田・上地、2024)。疲れやすい状態を長く経験してきた私たちは、たとえ疲れていたとしても、それは「自分は何もできない」ということを意味するわけではないと知っているのです。
学会での発表を聞きに来てくださった方の中には、「若い頃は疲れると自信がなくなっていたけれども、病気を経験してそうではなくなった」とおっしゃる方もいらっしゃいました。
「疲れることもあるけれど、それは自分の本来の能力や価値とは関係ない。」
人生の半分以上を体調が万全ではない状態で過ごすことになるこれからの高齢化社会で、多くの人にとって重要な価値観なのではないでしょうか。今はまだ多数派の社会では主流ではない考え方のようですが、社会全体がそのような価値観にソフトランディングできればいいのかもしれないと思います。
(2) 疲労は医療モデルと社会モデルの交差点
「医療モデル」「社会モデル」というのは、障害というものをどう捉えるか、という考え方です。「医療モデル」では、障害は個人の状態であると考え、障害のある人を障害のない状態にすることを目標とします。一方「社会モデル」は「障害は社会の側にある」と考えて「障害者」が何かをするときに多数派とは違う性質を持つことによって不利益(ハンディキャップ)があるのなら、社会の側で合理的配慮によって不利益が生じないようにするべきだ、という考え方です。
発達障害に関連する研究をしていると、何かにつけて「社会モデルで考えることの重要性」が強調されるのを目にします。人によっては、医療モデルから社会モデルに移行するべきだ、と言い切ることもあります。確かに、発達障害のある私たち当事者がこの社会で安心して暮らすために、社会モデルの考え方は非常に重要であることは間違いありません。
では、医療モデルというのは間違った古い考え方なのでしょうか。私は、少なくとも発達障害者における疲労の問題を解決するためには、社会モデルと医療モデルの両方が必要だと強く思います。
疲労の問題において、社会モデルの考え方が重要でることは、(1)で述べたように疲れやすさを隠すこと自体が大きな負荷になることからも明らかです。たとえ発達障害のある人の、生まれつきの体質によって生じる疲労が医療の力で解消されたとしても、能力主義が残っている限り発達障害に由来する生きづらさは消えないため、多数派の人と比べて負荷が大きくなる悪循環は消えないでしょう。
一方、どれほど疲れやすくても、体力的・気力的に無理のない範囲で仕事をすれば十分に生活できて、周囲の人からも暖かく受け入れてもらえる社会が実現したとしたらどうでしょうか。仮にそのような社会になったとしても、人生の中でやりたいことが肉体的・精神的に負荷の大きい活動であったら、疲れやすいことによって実現できない場合も多いでしょう。また、自分自身で行わざるを得ない食事や入浴などの日常生活によって疲労を強く感じることは、やはり苦痛だと思うのです。
レデマガ読者さんの中にはいろいろな立場や、考え方をお持ちの方がいらっしゃると思います。これまでお話してきたように、疲労というのは1つの考え方だけでは理解しきれない複合的な問題です。当事者や家族だけではなく、医療、福祉、教育、そしてそれらの制度設計など、多様な背景をもつ人々が協力して立ち向かうことが必要なのだと私は思っています。
さて、今回は発達障害のある私の主観的な疲労についてお話ししましたが、次回、最終回は家族から見た「疲れやすい発達障害者」について、私のパートナーである瀬戸川さんをゲストに迎え、考えてみたいと思います。
引用文献
Frost, D. M., & Meyer, I. H. (2023). Minority stress theory: Application, critique, and continued relevance. Current opinion in psychology, 51, 101579.
Jaime-Lara, R. B., Koons, B. C., Matura, L. A., Hodgson, N. A., & Riegel, B. (2020). A qualitative metasynthesis of the experience of fatigue across five chronic conditions. Journal of pain and symptom management, 59(6), 1320-1343.
仲田真理子・上地花奈 (2024)「成人における『疲労の意味』~実際に感じている疲労感との関連~」. 第20回日本疲労学会総会・学術集会. 大阪.
O'Sullivan, J. B., Ryan, K. M., Curtin, N. M., Harkin, A., & Connor, T. J. (2009). Noradrenaline reuptake inhibitors limit neuroinflammation in rat cortex following a systemic inflammatory challenge: implications for depression and neurodegeneration. International Journal of Neuropsychopharmacology, 12(5), 687-699.
Primdahl, J., Hegelund, A., Lorenzen, A. G., Loeppenthin, K., Dures, E., & Esbensen, B. A. (2019). The experience of people with rheumatoid arthritis living with fatigue: a qualitative metasynthesis. BMJ open, 9(3), e024338.
◆仲田真理子(なかた・まりこ)
筑波大学人間系助教。
専門は行動神経内分泌学。ホルモンと社会行動の研究の傍ら、疲労の研究をはじめる。自身が発達障害(自閉スペクトラム症/ASD・注意欠如多動症/ADHD)の当事者であることから、発達障害のある人のための通院・服薬に関する理解促進パンフレット「発達障害の当事者とまわりの人のための薬はじめてガイド」を制作し、無料で配布する活動を続けている。パンフレットは、webサイトよりアクセシブルPDF版をダウンロードできるほか、サイト内の「お申し込みフォーム」より無料で紙の冊子の発送を依頼することができる(病院や学校などには、一度に大量に発送することも可能)。
■□ あとがき ■□--------------------------
次回メルマガは、10月24日(金)の予定です。
▼YouTube動画 レデックス チャンネル ▼
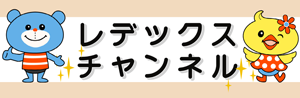


 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




