■ 連載:「疲れやすい」ってどういうこと?~家族の視点~
■□ コラム:映画『スノードロップ』-日本人の弱者に対する本質を問う物語
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
───────────────────────────────────…‥・
■ 連載:あまり知られていない発達障害のある人の疲労について第4回「疲れやすい」ってどういうこと?~家族の視点~(最終回)
───────────────────────────────────…‥・
レデマガ読者の皆様、こんにちは。筑波大学の仲田真理子です。連載「発達障害と疲労」、第3回では、発達障害の当事者である私の視点から、疲れやすいということはどのようなことかご紹介しました。第4回では、私のパートナーである瀬戸川剛さんに、発達障害のある疲れやすい人と一緒に暮らすということについて聞いてみたいと思います。
仲田:今日はありがとうございます。今日は家族から見た「疲れやすい人」について聞かせてください。まずは簡単に自己紹介をお願いします。
瀬戸川:富山大学の瀬戸川です。大学では、脳科学の基礎研究を行っています。仲田さんとは大学院の時に知り合って、以来10年ちょっと一緒に生活しています。
仲田:今はお互いの職場が遠いので、つくばと富山で離れて暮らしていますが、同じ専攻の同学年だった大学院時代の5年間と、働き始めてからも1年間だけつくばの家で一緒に暮らしていました。ずっと一緒にいると、元気ではないときの様子も知ることになります。学生時代の私はかなり疲れていたと思うのですが、瀬戸川さんからみてどうでしたか?
瀬戸川:当時は確かに一日中寝ていることが多いなぁとは思っていましたが、疲れているとはあまり考えていなかったです。
仲田:そうだったんですね。学生時代はいつも眠く、何をするのもしんどかったことを覚えています。今思うと疲労感がひどかった、ということなのですが、当時は私自身も「疲労」だとはっきりと自覚してはいませんでした。瀬戸川さんは、パートナーがずっと家で寝ていることについてどう思っていましたか?
瀬戸川:病気の話は聞いていたので、それによるものなのかな、とは思っていました
仲田:そういえば、最初は発達障害の診断がついておらず、「おそらく統合失調症」ということで通院していたのでした。
瀬戸川:それで別にこちらの生活に悪い影響があるというわけではなかったので、正直そこまで気にはしていなかったですね。
仲田:悪い影響があるというわけではなかった!?それを聞いて少し驚いたのですが、もう少し詳しく聞かせてください。パートナーがずっと寝ていたら、なかなか一緒に遊びに行けなかったりして嫌じゃないですか?
瀬戸川:当時は朝から夕方までずっと実験で、休みの日もそういう生活をしていたので、朝起きて仲田さんが寝ていてもそのまま自分は外出していました。そして、自分が帰宅するころには起きていたので、特に問題は感じなかったです。
仲田:たしかに、そちらから見ればそうかもしれない。瀬戸川さんは毎日朝から晩まで大学に行って、帰ってきてからはきちんと生活もしていました。洗濯とか、掃除とか。だから私のほうでは生まれて初めて発達障害のない人の日常生活を間近で見て、かなり絶望したんだよね。研究の世界は競争社会なので、今後、こんな人たちと競争して勝って行かなければいけないのかって。それですごく自分が嫌になったり、投げやりな気持ちになったりしていました。だから相手もフラストレーションを感じているのかなと勝手に思っていました。
POINT 1: 疲労によって本人がフラストレーションを感じていたとしても、まわりの人が同じように感じているとは限らない。
仲田:じゃあ、瀬戸川さんにとっては、一緒に暮らしていてもそこまで大変には感じなかった?
瀬戸川:外にあまり遊びに行かないという自分の性格にはマッチしていたかもしれないです。
仲田:ああ、それは重要かもしれないですね。
瀬戸川:あと、途中から「ご飯を作るのは仲田さん、片付けするのは自分」という風に、お互い得意なことのみをするというようなルールにしたのがよかったのかも。
仲田:確かに、相手がやらなかったときは無理をして自分の苦手なことをする、ということは私たちの場合はなかったね。今もそうですが、瀬戸川さんが片付けなかったら私も片付けないし、私がご飯を作らなくても別に瀬戸川さんが無理をして作るということはありませんでした。そうすると、疲れていたり忙しい時は、洗ってない皿がたまってきたり、連日レトルトご飯になったりして、多くの人が思い描くきちんとした健康的な家庭生活にはなりません。でも、絵に描いたような生活をしなくても生きていけるし、良い関係を維持することのほうが衣食住そのものよりも重要だという部分は、二人の考え方が一致していたのだと思います。
POINT 2:無理をして元気な人の考えるきちんとした生活を目指さないことや、お互いの苦手ではないことを活かすという考え方は大事。
仲田:とはいえ、私は特に学生時代は、外食に行くとレストランでパニックになったりとか、掃除機の音がして別の部屋に逃げたりとか、友達と一緒に遊ぶときにすぐ帰りたがったりフリーズしたり、直前で行けなくなったりすることが結構な頻度でありました。健康な人ってあまりそういうことがないように思うのだけれども、それをそこまで大変ではないと思えるのはすごい。
瀬戸川:うーん、その程度のことって、たいていの人に対して感じるレベルからちょっとだけ大変さがプラスされただけという感じで、個人的には大したことなかった。
仲田:そうなんだ。私は、情報がうまく処理できなくなると静かにフリーズするタイプだから、そのせいかもしれない。でも、あれだけずっと一緒にいて、具合が悪くなることも多かったのに、大したことがないように見えていたのは意外でした。
瀬戸川:自分はそのあたりのほかの人と大きく違う点を、本人は困っていることもあるかもしれないけども、個性の一部だととらえていて、そういう個性が強い人は逆にうらやましい点だと思っていた。
仲田:なるほど、瀬戸川さん自身は自分にもっと個性が欲しいと思っていたんですね。
瀬戸川:そうだと思う。いつも疲れて寝ていた仲田さんだけど、短い起きている時間でちゃんと研究を進めているのなら(※仲田注:実際には、修了までに2年オーバーしています)、それはそれでもう十分すごいことだと。それであれば、長時間寝て、少しでも疲労が回復するのならいいじゃない、って思っていました。
仲田:瀬戸川さんにも複雑な気持ちがあったのかもしれないけども、私はこのように言ってもらったことで「私、ちょっとかっこいい?」って少し救われた気持ちになったことを覚えているよ。
POINT 3:疲れやすい体質だと本人は大変かもしれないが、周囲の受け取り方次第で「疲れやすさの意味」は変わる。
仲田:私が疲労の研究をはじめたのは、瀬戸川さんがアメリカ留学から戻ってきて、一緒に暮らし始めたことがきっかけなんだよね。瀬戸川さんと私では生活の中でできることの量が全然違うんだけれども、それをどう伝えればいいのかわからなかった。学生時代はなんだかんだ合わせてくれていたのだと思うけれども、久しぶりに一緒に住んだら生活のテンポがはやくなっていて、全くついていけないと感じたんだよ。なんとかして「あなたと私はできることの量が違うんだよ」って伝えたくて、それに科学的な根拠があるのかを調べていたら「疲労」に行きついたという経緯がありました。
瀬戸川:そうだったんだ。初めて聞いたかも。自分は当時、「疲労」といえば運動した後の肉体的な疲れくらいしか考えたことがなかったけども、新型コロナウイルスの後遺症を経験して、ようやくそれ以外の疲れも実感するようになってきました。
仲田:それはどんな感じだったんですか?
瀬戸川:誰かとしゃべっているときに、自分自身がしゃべっている内容が頭に入ってこない状況というか、頭の中がずーんと重い感じ。いわゆるブレインフォグ※ですね。
※ブレインフォグ(Brain Fog Syndrome)直訳すると「脳の霧」となり、頭の中に霧がかかったような状態で、集中力や記憶などの認知機能の低下がみられる。新型コロナウイルス感染症の後遺症の一つとして話題になった。
仲田:ブレインフォグがある例として、発達障害はよくでてくるよね。
瀬戸川:そう。なので、今になって思えば、学生時代の仲田さんがずっと寝ていたのも、頭の中がこういう感じだったのかなぁと。
仲田:私は毎日ずっとそういう状態だっていうわけではなくて、体調が悪い時だけそうなっていたよ。とはいっても、学生時代は体調が悪いことがほとんどで、1週間に半日ぐらい頭の中の霧が少しだけ晴れるときがあって、メールの返事とか、考える必要のあることは全部そのときにまとめてやっていた。ただ、手を動かす作業は、霧が晴れたときでもしんどいと思いながらやっていたなあ。瀬戸川さんは、ブレインフォグの時、作業がつらい、みたいなのは経験したことある?
瀬戸川:作業がつらい、はないですね。
仲田:え…?ブレインフォグのときも?1つ動作をするたびに、大きくMPが減って(精神的な疲労の強さをゲームのキャラクターが魔法や特殊能力を使うために消費するマジックポイント「MP」を使うことに例えています)、もうやめたいーみたいなことしか考えられなくなるやつだよ?
瀬戸川:運動に不調をきたすというわけではなく、あくまで頭の中がすっきりしないという疲労でした。
仲田:いやいや、運動そのものじゃなくて。何かの動作をすると、身体を動かすということと、身体をどう動かすか考えるということと、動きによって見えるものが変わるという3種類の情報を同時に処理しなきゃいけないから、筋肉じゃなくて脳が疲れる、みたいな感じだよ。
瀬戸川:多分、そうなる前に昼寝して回復します。
仲田:前に!?常にそういう感じではない?例えば、朝起きてすぐ歯を磨く時とか…。
瀬戸川:ないです。
仲田:ないの!?ブレインフォグのときもそうはならなかったのか…。
瀬戸川:ブレインフォグのときはあくまで認知的活動にのみ影響が出たって感じですね。新型コロナからはちゃんと回復していて、肉体的な活動は普通にできるのに、会話とかができなくなる感じ。
仲田:それはもう全然違う現象だね。ようやく仲間になれたと思ってたのに(笑)同じ言葉で語られていても、もしかしたら発達障害の疲労感とは完全に同じものではないのかもしれないですね。
瀬戸川:そうだね。そう考えると、たとえ一時的にブレインフォグを経験することはあっても、普段元気な人が、もともと疲労感が強い人を理解しようとするのはなかなか難しいかもしれない。
仲田:じゃあ発達障害特異的に疲労の研究をする意義っていうのは、やっぱりあるのかもしれないね。
瀬戸川:疲労を感じやすい人も世の中にいっぱいいて、それが原因で困っているんですよってことを広く知ってもらうことが重要なんだと思う。
POINT 4:一言で「疲労」や「ブレインフォグ」と言っても、その実態は人によって、あるいは病気や障害の種類によって様々である可能性が高い。
ということで、今回はゲストの瀬戸川さんとともに、私たちの疲労について語り合ってみました。疲れ方は多様であるという結論になりましたが、そこに発達障害そのものがどのように関わっているかは、まだわかっていないことが多くあります。私たちも、少しずつですが、他の研究者と一緒に、謎解きを進めていけたらいいなと思っています。
これまで4回にわたりお読みくださった読者の皆様、ありがとうございました。
◆仲田真理子(なかた・まりこ)
筑波大学人間系助教。
専門は行動神経内分泌学。ホルモンと社会行動の研究の傍ら、疲労の研究をはじめる。自身が発達障害(自閉スペクトラム症/ASD・注意欠如多動症/ADHD)の当事者であることから、発達障害のある人のための通院・服薬に関する理解促進パンフレット「発達障害の当事者とまわりの人のための薬はじめてガイド」を制作し、無料で配布する活動を続けている。パンフレットは、webサイトよりアクセシブルPDF版をダウンロードできるほか、サイト内の「お申し込みフォーム」より無料で紙の冊子の発送を依頼することができる(病院や学校などには、一度に大量に発送することも可能)。
───────────────────────────────────…‥・
■ コラム:本や映画の当事者たち(16)映画『スノードロップ』-日本人の弱者に対する本質を問う物語
───────────────────────────────────…‥・
タイトルからもわかるように、いわゆる障害や病気などの当事者といわれる人たちが描かれている本や映画、DVDなどを紹介します。
蒸発して10年前に帰ってきた父と重度の認知症の母、娘の直子は、3人で肩を寄せ合って生きています。父が持病の悪化により新聞配達ができなくなり、生活保護の申請を考えるようになります。直子は、ケースワーカー・宗村とのやり取りを重ねて申請作業を進め、生活保護申請はほぼ通る状況となりました。そんな夜、父は直子に心中を持ちかけますが……。
これは、2016年に起こった一家三人の心中事件をベースにしたフィクション。この事件は、日本の現代の貧困問題を象徴していると思います。親子の選択の背景には、日本社会に根強く残る貧困への差別意識が存在しているように思えるのです。
15年ほど前、大病から生活保護を受給していたという監督が描く今作には、ふるえるほどの哀切がにじんでおり、私には他人事には到底思えません。近年、不正受給の問題なども出ており、生活保護制度を利用すること自体が非難の的になり敬遠される傾向もあります。
吉田監督からは、「映画を通じて、この矛盾した行動の真意を問い、生活保護を受給することの意味を自分なりに追求してみたいと思い映画を制作するに至りました。非常に重い題材を元にしていますが、自分なりの希望をこの映画に託したつもりです」との言葉がありました。
夕食のおかずのかぼちゃをコトコト煮る、重度の認知症の母に対する直子の柔らかな介護姿などを描いて、非常にリアルな庶民の生活が見る側にも迫ってきます。決して華美ではないが、慎ましく生きている3人家族の生活を脅かす貧困という現実。確かに非常に重たい題材ではあります。しかし、最後に映されたスノードロップ(待雪草)の可憐な姿に、直子の未来と日本の貧困対策への希望が垣間見られたように思えるのは私だけでしょうか。
この映画は、第45回カイロ国際映画祭メインコンペティション部門で入選を果たしています。2024年11月に開催された第45回カイロ国際映画祭internationalcompetition部門(メインコンペティション)に映画「スノードロップ」が選出されました。世界12大映画祭の一つであるカイロ国際映画祭は中東地域最大の歴史ある映画祭であり、第44回映画祭では映画「ある男」がinternationalcompetition部門にて最優秀脚本賞を受賞しています。
映画「スノードロップ」が映画祭のメインコンペティション部門に選出されたのは快挙であり、1200人収容のオペラハウスシアターでは大勢の観客に出迎えられ、大好評を博しました。その他、アジア映画祭として注目度の高い第19回JOGJA-NETPAC_ASIANFILMFESTIVALAsianPerspective部門にも招待上映が決まっています。
日本人として、弱者を切り捨ててしまうことができるのか…….是非とも見て感じて、考えてほしいと思います。
出演:西原亜希、イトウハルヒ、小野塚老、みやなおこ、芦原健介、丸山奈緒、橋野純平、芹澤興人、はな
監督・脚本:吉田浩太
プロデューサー:後藤剛
撮影監督:関将史
撮影:関口洋平
録音:森山一輝
美術:岩崎未来
衣裳:高橋栄治
メイク:前田美沙子
スチール:須藤未悠
助監督:工藤渉制作 古谷蓮
主題歌:浜田真理子「かなしみ」
製作:クラッパー
宣伝・配給:シャイカー
配給協力:ミカタエンタテインメント
2024/98分/ステレオ/DCP
展開:2025年10月10日~新宿武蔵野館にて公開
◆はら さちこ
ライター。
編集制作会社にて、書籍や雑誌の制作に携わり、以降フリーランスの編集・ライターとして活動。障害全般、教育福祉分野にかかわる執筆や編集を行う。障害にかかわる本の書評や映画評なども書いている。
主な編著書に、『ADHD、アスペルガー症候群、LDかな?と思ったら…』、『ADHD・アスペ系ママ へんちゃんのポジティブライフ』、『専門キャリアカウンセラーが教える これからの発達障害者「雇用」』、『自閉症スペクトラムの子を育てる家族を理解する 母親・父親・きょうだいの声からわかること』『発達障害のおはなしシリーズ』、『10代からのSDGs-いま、わたしたちにできること』などがある。
■□ あとがき ■□--------------------------
11月2日は新潟での日本発達障害学会でポスター発表です。内容は「知能検査を子どもだけで行えるクラウドサービスの開発」。9月26日には旭川の日本小児リハビリテーション医学会で同じテーマで口頭発表をしました。教育関係者と医療関係者に当社デジタルサービスをしってもらえればと思います。
次回メルマガは、11月7日(金)に刊行予定です。


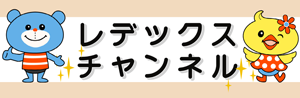
 メルマガ登録はこちら
メルマガ登録はこちら




